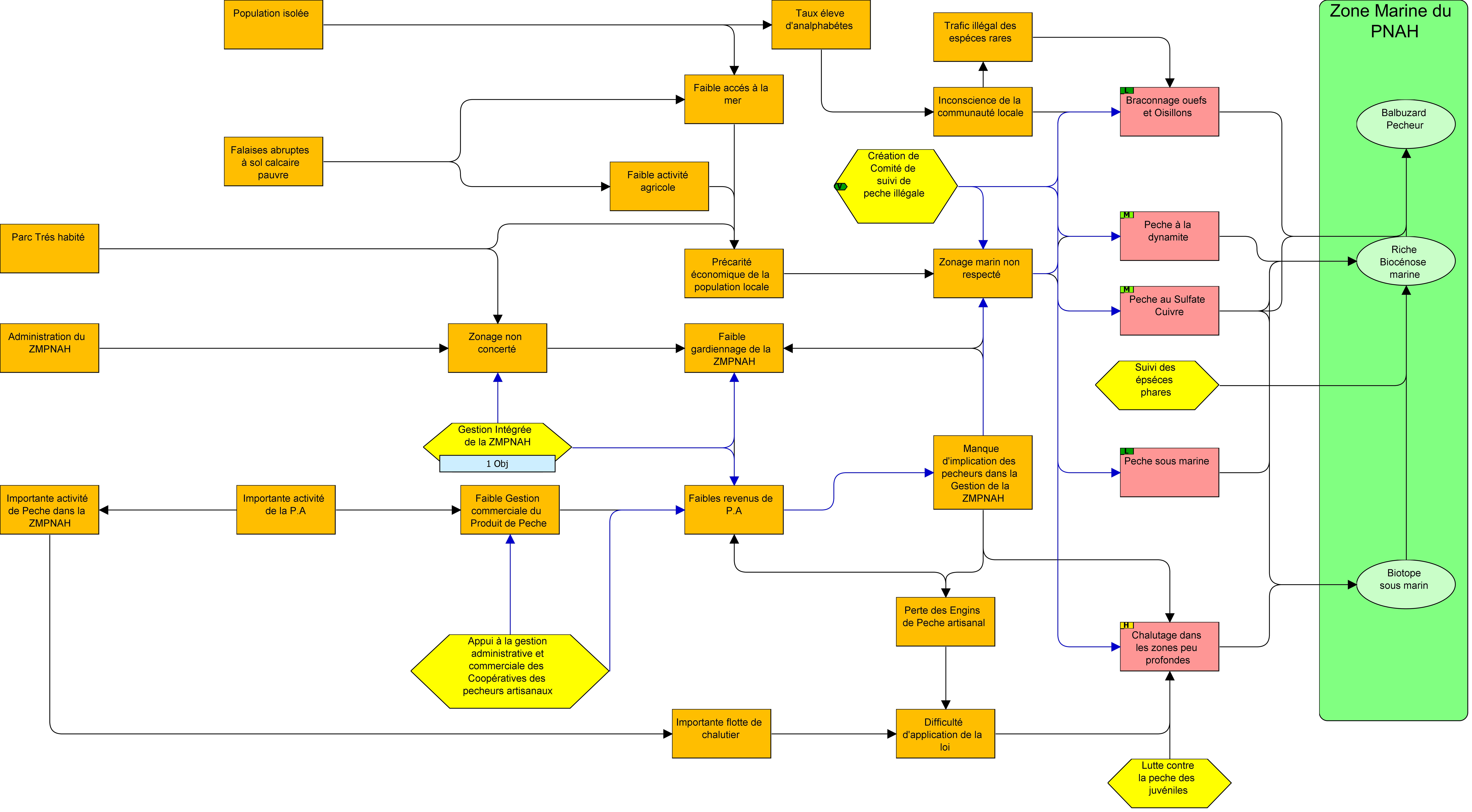目標
- 対象となる調査とモニタリングを実施することにより、絶滅危惧種に関する知識を向上させる。
- 沿岸・海洋資源、ビオトープ、絶滅危惧種個体群の管理に地域社会を参加させる。
プロセス
プロジェクトを開始し、関係者間の信頼関係を確立するためにワークショップを開催した。参加型ワークショップには、国家憲兵隊、水・森林・砂漠化高等弁務官事務所海洋漁業局、地元漁業コミュニティ、NGO AGIRから少なくとも50名の代表が参加した。
すべての利害関係者を巻き込むため、多者構成による管理委員会が選出された。委員会はアル・ホセイマ州知事が主宰する。
AGIRチームと漁業者は、資源と生息地の保全状態に関するモニタリングと参加型評価の調査に参加する体制を整えている。絶滅の危機に瀕しているフラッグシップ種のモニタリングは、関係当局と連携して行われている。
MPA内の違法行為の監視・取締プログラムのモニタリングのため、毎週現地視察が実施された。
新たな保全状況(生息地の回復、絶滅危惧種、海洋資源)を反映した科学的報告書を作成。