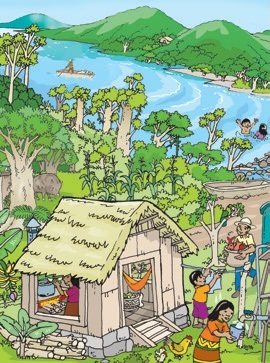共同適応計画
ポルト・セグロ市計画は、市環境評議会の管理の下、参加型アプローチで策定された。この協議会は、地方政府、州政府、地域コミュニティ、NGO、観光部門の代表によって構成されている。ワークショップや会議には、さまざまなセクターから120人以上が参加し、多様な協力関係を築き、地域の脅威と機会を特定し、地域についての知識に基づいて具体的な活動を提案した。市町村議会は、最終的な計画を修正・承認し、それを公表して一般に配布した。共同管理構築のアプローチは、現在、他の自治体の計画にも導入されており、他の9つの近隣自治体における大西洋岸森林の保全と回復のための計画構築の参考として利用されている。
- 当初から参加型のプロセスであったこと - 統治システムが明確に定義されていたこと(環境自治体協議会)。
- 様々な利害関係者が自治体計画の策定に参加するための関心を高めるには、動員段階が重要であった。複数のセクターが参加することは、さまざまな生態系や活動を包括的に分析するために重要である。自治体の事務局がプロセスに参加したのはわずかである。