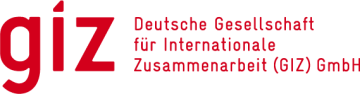
気候変動への耐性とアグロエコロジーのための生態系サービスとしての受粉の促進

ヒマーチャル・プラデーシュ州のリンゴ園では、受粉媒介者の減少が果実の品質、収量、農家の収入を脅かしている。生産と気候変動への耐性を向上させるため、インド農業・食品セクターのためのグリーン・イノベーション・センターは、パートナーであるY.S.パルマール園芸林業大学(UHF)およびキーストーン財団と協力し、生態系サービスとしての受粉を推進した。シムラとクルで実施されたこのプロジェクトは、 セイヨウミツバチなど 在来の受粉媒介者の保護と科学的な受粉管理に重点を置いた。活動には、養蜂や蜂蜜加工に関する農民や零細起業家の研修、泥の巣箱や蜂ホテルの設立促進、季節ごとの蜂相の向上、大規模な意識向上キャンペーンを通じた農薬使用の削減などが含まれる。受粉の改善により、果実の大きさと品質が向上し、6月の落果が減少し、気候や天候に関連するリスクへの回復力が高まる一方、養蜂は農民に多様な収入機会を提供している。
コンテクスト
対処すべき課題
環境問題への挑戦
野生のミツバチ、チョウ、ガ、ミツバチを含む昆虫受粉媒介者の個体数は、単一栽培農法、過剰な農薬使用、自然生息地の喪失、気温上昇などの気候変動の危険性により減少している。これにより生物多様性が脅かされ、果実の着果や持続可能な農業に不可欠な受粉サービスの利用可能性が低下している。
社会的課題:
受粉方法、受粉媒介者の生態学的役割、有害な農薬使用によるリスクに関する知識は限られている。このような理解がなければ、受粉支援対策は広く採用されず、しばしば損なわれる。
経済的課題:
受粉不良はリンゴの収穫量と果実の品質を低下させ、農家の収入に直接影響する。果実が小さかったり不揃いだったりすると価格が下がり、早すぎる落果は市場価値のある農産物をさらに減らしてしまう。
所在地
プロセス
プロセスの概要
花粉媒介者の保護に多角的に取り組むことで、各ブロックは互いに補完し合っている。広範な意識向上により、農業コミュニティ全体に変化をもたらす基盤が構築され、地域の意思決定者や学生など、将来の農業慣行に大きな影響を与える他の関係者も関与した。ミツバチに優しい農法の推進や農場内での営巣地の設置といった実践的な対策により、農家は花粉媒介者の個体群を積極的に保護・支援できるようになった。さらに養蜂と蜂蜜加工を導入することで、直接的な生計利益を生み出し、持続可能で花粉媒介者に優しい果樹園経営の経済的インセンティブを強化した。リンゴ栽培において、より持続可能で花粉媒介者に優しい農法への転換を可能にするために、農家、コミュニティ、システムの各レベルで必要とされるさまざまな変化に対応するためのビルディング・ブロックである。
ビルディング・ブロック
リンゴ栽培における在来昆虫受粉媒介者の重要性の啓発
地域の生物多様性と受粉サービスは、特に化学投入物の使用に関して、地域のすべての農民、地域機関、その他の利害関係者が行う集団的な選択によって影響を受ける。より広範な意識と行動変容を促進するため、プロジェクトは直接の受益者以外にも啓発キャンペーンを展開した。シムラとクル全域で、農業関係者、学生、地元の意思決定者など2,000人以上を対象とした。意識向上ワークショップは、地元のグラム・パンチャヤット(地方統治機関)における15の村レベルの会合、20の学校、大学、産業訓練センターでのセッション、49の地元セルフ・ヘルプ・グループとのワークショップで実施された。
より的を絞った構成要素として、プロジェクトは6つの協力農家生産者企業(FPC)と綿密なワークショップを実施し、農場での慣行を変えることを直接目的とした。このワークショップやその他のキャンペーンイベントでは、参加者が具体的な問題を共有し、課題について話し合い、自らの経験や地元の慣行をもとに、有害な農薬や化学肥料の代替案を提案した。
受粉媒介者の管理と保護に関するモジュールは、UHFと園芸局(DoH)を中心としたプロジェクトの受粉管理研修に組み込まれた。
実現可能な要因
プロジェクトでは、UHFと保健省との合同ワークショップを実施し、政策・研究機関からのフィードバックを可能にした。農民が理解しやすい簡潔なスローガンや説明とともに、現地語で魅力的な啓発資料が作成された。村の集会や教育機関、地元の見本市を対象としたアウトリーチ・キャンペーンを実施し、最大限の働きかけを行いました。
教訓
重要な教訓は、行動変容コミュニケーションは文化的背景を考慮しなければならないということである。さらに、有害な化学物質が使用されていることを認識させるためのナレーションは、それを製造している民間企業や、それを使用している農家をターゲットにしてはならず、人間と環境の健康への悪影響に焦点を当てなければならない。
野生の花粉媒介者を守る
最も簡単で安価な受粉対策は、果樹園におけるミツバチなどの受粉媒介者の保護である。これらの昆虫は果樹の受粉に不可欠な役割を果たしているからだ。この目的のため、プロジェクトでは、保護農法と花粉媒介者のための農場内生息地づくりを組み合わせた二重アプローチを推進した。
農家には総合的病害虫管理(IPM)が紹介され、化学農薬の代替や、害虫の発生を抑えるための偵察や剪定などの技術が強調された。また、開花期の農薬使用を避け、必要なときだけ、適切な技術で、適切な量を散布し、年間を通じて花の多様性を維持し、養蜂家と緊密に連携するなど、ミツバチに優しい慣行を採用するよう奨励した。これらの対策は、花粉媒介者への被害を減らし、投入コストを削減し、残留化学物質を最小限に抑えるのに役立つ。
こうした実践を補完するために、農家は泥の巣箱や蜂のホテルなど、地元で作られたシンプルな巣箱を設置し、在来種のミツバチや野生の花粉媒介者を支援している。これらの在来種は現地の条件によく適応しており、気温が低くても活動を続けることが多いため、開花の重要な時期には特に貴重な存在となる。
実現可能な要因
- 農家の既存の知識や利用可能な資源に沿った、低コストで導入しやすい手法の推進。
- 泥の巣箱や蜂のホテルのような簡単な営巣構造の建設に、地元で入手可能な資材を利用する。
教訓
- 新しい技術の試験的導入には、当初から農民が密接に関与したことで、より広範な導入が保証された。
- UHFによるベストプラクティスの普及と科学的支援により、制度的な定着が図られた。
養蜂と蜂蜜加工による農民の生計の多様化
受粉関連の利益を補完し、所得の多様化を促進するため、プロジェクトはリンゴ栽培世帯の追加的な生計活動として養蜂と蜂蜜加工を導入した。農民や零細起業家は、在来種のミツバチApis ceranaの利用に重点を置きながら、養蜂を既存の農業システムに組み込むための支援を受けた。参加者は養蜂の実践、巣箱の管理、ハチミツや関連製品の付加価値加工に関する研修を受けた。これらの活動は、代替収入源を通じて回復力の向上に貢献し、花粉媒介者の個体数を保護する経済的インセンティブを生み出す。
実現可能な要因
- 現地の気候や景観に適応した在来種のミツバチの入手可能性
- プロジェクト活動の一環として提供される訓練と技術指導
- ハチミツの加工と販売による付加価値の可能性
教訓
- 養蜂はリンゴ農家にとって生計の足しになる
ハチミツ販売などの経済的インセンティブは、花粉媒介者に優しい農法を強化することができる。
影響
環境への影響
このプロジェクトは、野生の受粉媒介者の保護とセイヨウミツバチのような在来種の促進に貢献し、リンゴ園の生物多様性と生態系のバランスを改善した。農薬使用の削減、花の多様性の拡大、農場内の生息地の創出により、受粉サービスが向上した。また、生息地の保全は花粉媒介者の気候変動への適応を助け、受粉サービスの向上はリンゴの収量と品質の回復力を高めます。
社会的影響
技術的なトレーニングだけでなく、プロジェクトは農民、自助グループ、地元機関を動員し、花粉媒介者の保護を日々の農業慣行に組み込んだ。村の会合、学校でのセッション、地域の統治組織との関わりは、持続的な意識を生み出し、ヒマーチャル・プラデーシュ州の農業コミュニティに生物多様性に配慮したアプローチを定着させるのに役立ちました。
経済的影響
受粉が改善されることで、着果が促進され、よく発達したリンゴの割合が増え、より強い種子と果実の発達を支えることで早期落果が減少します。その結果、農家は市場に出せる収量を増やし、果実の品質を向上させ、価格を上げることができる。養蜂とハチミツ加工への多角化により、従事農家の収入が強化され、花粉媒介者を保護する経済的インセンティブが生まれるとともに、農家の生計が気候変動に強くなりました。
受益者
シムラとクルーの農家と零細企業家80人が、養蜂と受粉に関する研修を受けた。リンゴ栽培農家は収穫量と収入の向上という恩恵を受けた。在来のミツバチや野生の受粉媒介者は、生息地の回復と農薬使用の削減という恩恵を受けた。
グローバル生物多様性フレームワーク(GBF)
持続可能な開発目標
ストーリー
37歳の農夫キシャン・チャンドは、4人の家族とともに、インドヒマラヤ山脈のふもとに位置するマナリ近郊の風光明媚な山村で、小さなリンゴ園の手入れをしている。観光業を除けば、リンゴ栽培はヒマーチャル・プラデーシュ州の経済に5%貢献しており、村の経済が依存する主要部門である。しかし、花粉媒介者の減少や農作物の生産性低下という課題は、彼らの農園にも及んでいる。
キシャン氏は、自分のビジネスを始めたいと常に熱望し、自分たちの課題に対する解決策を模索していたため、農民生産者組織KPMの会員であることを利用して、GICによる複数の研修に参加した。彼は栄養管理、受粉管理、総合的害虫管理、キャノピー管理などのコースに参加した。
2021年までに、研修で培ったミツバチの行動、巣箱管理、ハチミツ採取技術、病気対策に関する知識と技術により、彼は自ら養蜂家となり、家族の生計手段を増やすことができた。彼はまた、箱型巣箱1つとセイヨウミツバチのコロニーを与えられ、現在では他の農家に箱型巣箱を貸してそれぞれの果樹園で受粉させる一方、自分の農園でも箱型巣箱の数を増やしている。
キシャン氏はミツバチのコロニーを少しずつ増やし、25箱のセイヨウミツバチを飼育するまでになった。最近、彼は45箱のISI製10~11枠の蜂箱を購入した。その内訳は、1箱18ユーロのスーパー巣箱が10箱、1箱15.5ユーロの普通の巣箱が35箱である。
2021年から2024年にかけて50kgの蜂蜜を生産し、40kgの蜂蜜を1kgあたり12~14.5ユーロで販売した。さらに、他の農家に蜂箱を貸し出す際には、1箱あたり月9~12ユーロを請求している。キシャンは現在、蜜蝋や女王蜂の飼育など、養蜂から他の収入を得る活動や製品を追求するためのステップを踏んでいる。彼はすでに半キログラムの蜜蝋の生産に成功している。
養蜂をさらに発展させるため、キシャン氏は自分のスキルを活かして商業養蜂ビジネスへの移行を目指している。彼の焦点は、ミツバチの巣箱とミツバチを増やし、ハチミツやその他の蜂産品を生産することだ。ミツバチの健康と製品の品質を確保しながら、これらの製品の付加価値を高めることが長期的な戦略である。




