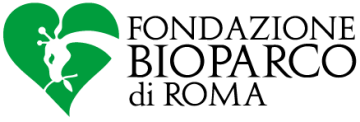アペニンキイロヒキガエルの保護

アペニンキイロヒキガエル(Bombina pachypus)はIUCNレッドリストで絶滅危惧種に指定されているイタリア固有の両生類である。
ほとんどの個体群は6~20頭にまで減少している。
我々は、個体数が10以下と激減した2つの群れにおける再繁殖プロジェクトについて報告する。
調査地におけるこの種の脅威は、プールの乾燥化とイノシシによる生息地の改変であった。
2005年から2013年まで個体数は安定していたが、2012年に脅威を軽減するために2つの対策が実施された:1)乾燥化を避けるためにプールを増設し、湧水を供給する、2)イノシシがプールを利用しないように各プールに柵を設置する。 2年後、個体数の増加は観察されなかった。
私たちは人工飼育施設で育てた個体の再繁殖を通じて個体数を増やすことを目的とした4年間(2014~2017年)のプロジェクトを開始した。 全体で67匹の若いヒキガエルを放した。
コンテクスト
対処すべき課題
このプロジェクトの主な目的は、モンティ・ナヴェーニャ・エ・チェルヴィア自然保護区、ローマ・ビオパルコ財団、ローマ大学科学部を主なパートナーとして、地域レベルでの保全戦略を策定することである。具体的には、このプロジェクトは以下の課題に取り組むことを目的としている:
1 再飼育の前に、選択された個体群に対する主な脅威を軽減する。例えば、プールの早期干ばつやイノシシ(Sus scrofa)による湿地の改変など。
2 再飼育のために選ばれた同じ場所から野生で採集された卵から、1 歳変態個体の適切な飼育下繁殖個体群を生産する。
4 飼育下で飼育された1歳のヒキガエルを、2014年から2017年にかけて毎年4回、野生に放す。
5 再接種の4年目以降に、元の個体数を倍増(少なくともN>20)させる。
6 長期的に自給自足可能なボンビナ・パキプスの2つの個体群を確立する。
所在地
プロセス
プロセスの概要
各ブロックのつながりと相互作用は順次的である。各ブロックは次のブロックのための準備であり、プロジェクト全体が完全に成功するように、前のブロックの実現を無視することはできない。
脅威緩和行動を計画するためには、アペニンエキヒキガエルの個体群の保全状況をモニタリングすることが不可欠である。さらに、緩和行動の影響を長期的に評価し、さらなる強化行動(再補充)の必要性を理解する必要がある。
ビルディング・ブロック
事前のモニタリング
行動前のモニタリング活動は、ベースラインを定義し、プロジェクトの明確なタスクが対象種の保全状況に与える影響を定量化するために必要である。私たちの場合、2005年から2013年まで2つの調査個体群を捕獲-標識-再捕獲法でモニタリングした。その結果、個体数は18頭(1個体群につき9頭)で、9年間のモニタリングで新たに個体群に加わったのはわずか3頭で、安定した個体数を維持した。それぞれの場所は、3月下旬から9月下旬までヒキガエルが産卵する1つか2つの小さな浅瀬で構成されていた。
実現可能な要因
活動前のモニタリングは、プロジェクト開始前に定義されなければならない。モニタリングは、標準化された方法論(すなわち、同じ労力とアプローチ)で構成されなければならず、その結果、時間的・空間的な再現性が可能になり、具体的な保全活動の影響を定量化することができる選択された指標の定量化が可能になる。
教訓
私たちの事前のモニタリングは、プロジェクトの全期間を通じて同じスタッフによって行われた。これは、同じ労力と効率性を意味し、サンプリングや年による一貫性の欠如を軽減する。
脅威の緩和
個体の移動(人工繁殖の有無にかかわらず)を伴う具体的な保全活動を行う前に、発生した脅威の評価とその緩和・除去は、活動の成功のために必須である。
調査地でこの種に観察された主な脅威は、繁殖期の初期(つまり6月)に池が乾燥するリスクが高いことと、イノシシによる池の改変であったため、2012年にはこれらを緩和するために2つの主な保全活動が実施された:
- 多年生湧水を水源とするプールを各サイトに4つ増設し、水生期間を3月から10月まで延長した;
- イノシシが飲水や水浴びに池を利用しないよう、各池に柵を設置した。
実現可能な要因
対象種の保全状態に影響を及ぼす、効果的で潜在的な脅威を網羅的に明らかにし、描写するためには、種の生物学と生態学に関する徹底的な知識が必要である。
教訓
対象個体群の保全に影響を及ぼす主な脅威の緩和/根絶は、短期/中期的に有意な影響(マイナス傾向の逆転)を達成するには不十分である可能性がある。短期的に個体群を増加させるためには、緩和行動と個体群の移動 を伴う具体的な保全介入を組み合わせなければならない可能性がある。対象となる種が長命で、世代率が長い場合、短期的には脅威緩和行動による影響が観察されない可能性が高くなる。実際、ボンビナ・タキプスは長寿種であり、約30歳に達することができる。
再入荷
脅威緩和措置から2年経っても個体数の増加が見られないため、2014年に個体数の増加を目的とした4年間の再繁殖プロジェクトを開始した。
このプロジェクトでは、卵の段階でボンビナ・パキプスの個体数の一部(30~40%)を野生で採集し、飼育下で発育させ、その後、同じ採集場所で変態した個体を放す。
ヒキガエルの人工飼育はすべてBioparco財団の施設で行われ、腹部の色彩パターンが完全にはっきりするまで個体が飼育された。
全体で67の若い個体がリリースされた(2014年に20、2015年に19、2016年に16、2017年に12)。
放流後のモニタリングにより、ヒキガエルの再捕獲率は年によって大きく変動することが明らかになった。 2018年には合計21個体を再捕獲した:2014年に放された10個体、2015年に放された2個体、2016年に放された4個体、2017年に放された5個体である。原始的な個体群は安定した状態(13個体)を維持し、新たに加入した個体は少なく、損失もあった。2018年末には、放流された21個体の純増と自然加入による若干の増加により、原始個体数は2倍になった。
実現可能な要因
卵の段階から1歳の個体を生産するためには、十分な施設と多くの人材が必要である。
再飼育の成功をモニタリングするには、複数年にわたるプロジェクトと十分な労力(人的・経済的)が必要である。
教訓
性成熟間近の変態個体を放すことで、腹部の色彩パターンによる個体識別が可能となり、卵や幼虫の段階でピークに達することが知られている死亡率を大幅に減少させることができたはずである。
飼育下で繁殖させたヒキガエルは、Bombina pachypusの減少した個体群の再繁殖に利用できる。
再繁殖は、確率的または予測不可能な出来事による失敗の可能性を克服するため、複数年にわたるプロジェクトに沿って、明確な段階を踏んで個体を放すことによって行うべきである。
個体の再捕獲率が年によって大きく変動することや、放流した個体の多くが再捕獲に失敗すること(死亡や分散など)の背後にある真の原因を特定することは、局所的なスケールで高いサンプリング努力をもってしても非常に困難である。
影響
私たちの解決策の主なプラス効果は、放流した21匹のヒキガエルと自然加入による若干のヒキガエルの純増で、元の個体数を2倍にすることができた。
さらに、再飼育されたヒキガエルは何年にもわたって繁殖を繰り返し、飼育下で繁殖された個体は、野生動物で報告されている成熟年齢(3年)よりもかなり早い13ヶ月で繁殖可能な状態になった。このように
飼育下繁殖個体群の再繁殖が良好な結果であったことを考慮し、考慮されたデームにおけるさらなる個体の放流は中止されたが、モニタリングは現在も継続中である。
再繁殖が成功したことから、以前実施された2つの繁殖地に近い場所に、より大きな湿地が新たに建設された。モニタリングは現在も継続中である。
受益者
自然保護区は、絶滅危惧種の保護活動から正味の利益を得ている。
介入地域に隣接する市町村の市民は、コミュニケーションや教育イベントに参加している。