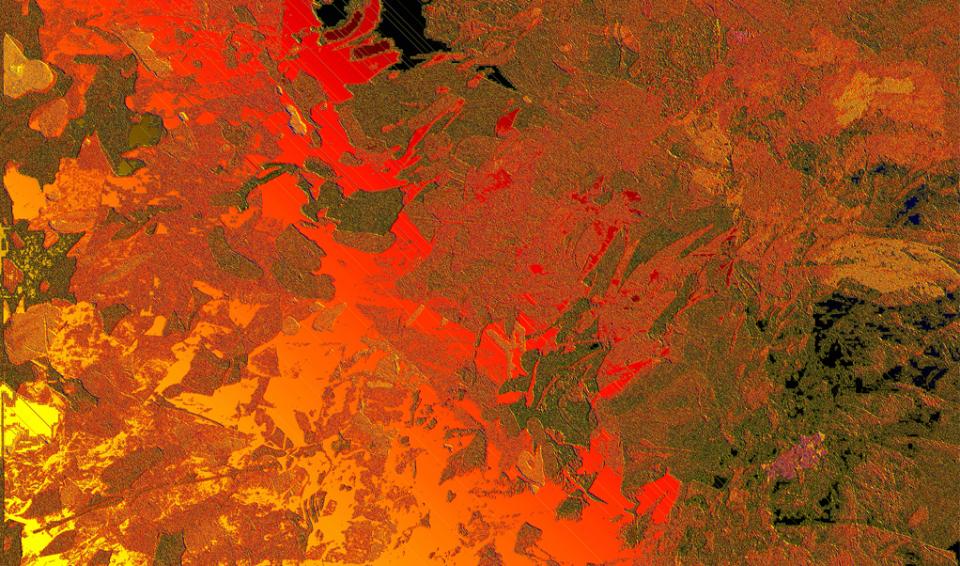オリーヴ・リドリー・ガメの保護の確保:開発と保全の共存のケーススタディ

ダムラ港の物語は、インドに大規模な深海工業港を建設する際に、絶滅の危機に瀕しているウミガメの個体数に害を及ぼさないよう、大手企業と世界的な環境保護団体が協力して取り組んだ物語である。開発の観点からは、この場所は完璧だった。しかし、保全の観点からは、インドの法律で保護されている世界最大級のウミガメの営巣地の近くに位置することに疑問があった。DPCL-Dhamra Port Company Limited(当時はタタ・スチールとL&Tの合弁会社)とIUCNの協力関係は、開発と自然保護が共存できること、そして人々のニーズと自然のニーズの両方を満たす責任ある方法で開発する方法があることを示している。このパートナーシップから学んだ教訓は、人々にとっても自然にとっても同様の好ましい結果をもたらす他のプロジェクトにも応用できる。
コンテクスト
対処すべき課題
このプロジェクトの大きな課題は、港湾建設とそれに続く長期的な港湾活動によってウミガメが深刻な影響を受けないように保護するためのセーフガードを確実に成功させ、継続させることだった。しかし、望ましい行動変容に関連する課題もあった。以下はその一例である:
- プロジェクトに対する関係者の抵抗。
- 主要な利害関係者の風評リスク
長期的にオリーブ・リドリーの個体群を確実に保護するという観点からは、ウミガメの死 亡の原因となっている地域社会の漁法を変えるなど、ウミガメの重要性に関する地域社会の 認識を高めることも重要であった。
所在地
プロセス
プロセスの概要
プロジェクトの3つの構成要素を通じて、開発と保全の両立という課題に対する全体的な解決策に到達した。それぞれのブロックがプロジェクトの異なる側面に取り組む一方で、これらすべてを組み合わせることで、ステークホルダーや関係者間の相互信頼と協力関係が強化され、短期的な成果と長期的な持続可能性の両方のための関与、対話、理解が可能になった。
ビルディング・ブロック
強力なパートナーシップとオープンなコミュニケーション
一般的に、民間セクターは環境問題に対して盲目的であると言われている。しかし現実には、民間企業は生物多様性に多大な投資をしている。このプロジェクトは、企業にとって環境問題への理解を深め、利益を超えて考えるという企業習慣を身につける機会となった。また、環境問題の専門家にとっては、ビジネスと開発の力学に対する理解を深め、自らの評価にボトムライン分析を取り入れることを学ぶ機会となった。
実現可能な要因
強固なコミュニケーションの実践は、パートナーシップと密接な関係にあった。環境団体やその他のセクターの間では、この問題に敏感であるため、プロジェクトに対するアプローチは、情報を透明化し、一般に公開することだった。パートナーは、自分たちが何をしているのか、何をしていないのか、そしてその理由を明確に説明した。情報は、ファクトシートやプロジェクトのウェブサイトを通じて、また公開討論会やミーティングに参加することによって公開された。
教訓
このほかにも、主要な利害関係者の間で情報が自由に行き交うよう、さまざまな取り組みが行われた。たとえば2009年初め、IUCNはオディシャ州ブバネスワールでダムラ港に関する協議技術ワークショップを開催し、その後、港の現場を視察した。この対話型フォーラムには、政府代表、民間セクター、国内外の一流の科学者、技術専門家、学者、地域コミュニティの代表など、多様な顔ぶれが集まった。報道機関との協力により、メッセージが全国レベルで広まるようにした。こうした努力は参加を促し、混乱を払拭するのに役立った。
科学と技術の専門知識
ウミガメに対する深刻な脅威として認識されている浚渫は、IUCNによって優先事項として特定された。 IUCNは、種の保存委員会のウミガメ専門家グループの専門家とともに、港湾作業中に従うべき浚渫プロトコルを設計・開発した。これには、ウミガメが浚渫船に引き込まれないようにするため、すべての浚渫船のドラグヘッドにウミガメ偏向装置を設置することも含まれた。このプロセスを監視するため、訓練を受けたオブザーバーがすべての浚渫船に 配置された。これらのオブザーバーは、流入管と越流管のスクリーンを年中無休でチェックした。これらの対策(偏向装置、スクリーン、人間の監視員)は、浚渫が「カメに優しい」ことを保証するために実施された。このような措置は、インドにおける浚渫活動の歴史において初めて実施された。
子ガメは本能的に明るい場所に向かって移動し、海から遠ざかるため、過剰なまぶしさは子ガメの注意をそらすことが知られている。このため、IUCN委員会の専門家は港湾の照明計画について具体的なガイドラインを提示し、港湾当局はこれを採用した。IUCNはさらに、タタ・スチールがこれらの照明の適切なデザインを特定するのを支援した。今日、ダムラ港は「ウミガメに優しい」照明を設置したインドで最初で唯一の港である。
実現可能な要因
IUCNはDPCLの環境管理計画(EMP)策定を支援した。この計画は科学的に強固であり、既存の法的要求事項を超えて実際に実施可能なものであった。最も重要なことは、EMPがDPCLの標準作業手順書(SOP)の不可欠な一部となるように設計されていることである。そのため、他のEMPとは一線を画している。
教訓
大規模なインフラは、生物多様性に配慮した設計が可能である。
コミュニティへの働きかけとガバナンス
IUCNがダムラ港のプロジェクトに参加したのは、港がオリーブの仲間であるウミガメに危害を加えるのではないかという懸念からだった。しかし、IUCNが問題を掘り下げていくうちに、カメの死亡率がすでに劇的に増加していることがわかった。インド野生生物研究所が作成した報告書によると、1980年代初頭には年間数千匹だったウミガメの死亡率は、1990年代半ばには1万匹以上にまで増加していた。機械化されたトロール漁業と刺し網漁業が死亡の原因であると見られている。
ウミガメの価値に関する地域社会の意識は低かった。これに対処するため、IUCNチームは伝統的なアウトリーチ活動だけでなく、創造的な教育プログラムなど、地域社会の感化活動に従事した。DPCLはまた、地元の村人が新しいスキルを身につけられるよう、コミュニティトレーニングセンターを設立した。
IUCNはまた、この地域の最大の問題のひとつであるトロール漁によるウミガメの死亡を減らすには、カメ排除装置(TED)の使用が有効であることを確認した。インドのNGOや科学者が過去に漁師たちとテストしたことがあったが、使用されていなかった。国際自然保護連合(IUCN)のDPCLチームは、この問題をよりよく理解するために、地元の漁業協同組合役員やコミュニティと幅広く協議しました。
実現可能な要因
トレーニング・ワークショップが開催され、この地域の漁民を対象としたTEDの実践的な試みが数多く行われた。地元の漁業コミュニティの慣習を変えることは、依然として大きな優先課題であるが、政策的解決策と組み合わせた長期的な教育プログラムが必要である。
教訓
この公的な場で取り組まなければならない最後の障害は、統治であった。当初、地元当局はウミガメの安全よりも漁業者の権利を重視していたようだ。しかし、理解が広まるにつれて、政府機関は全体的で長期的な解決策を提唱するパートナーとなった。漁業以外の収入を得る選択肢をコミュニティに提供するための代替生計訓練も行われた。
影響
パートナーシップの結果、DPCLはIUCNの支援を受けて環境管理計画(EMP)を起草した。EMPは、規制、方針、計画、実施、運営、管理、品質保証、モニタリングに対応している。また、変更管理に必要な手順や、安全、環境保護、地域社会との良好な関係の促進を優先する企業文化の発展についても詳述している。
継続的な調査と介入に資金を提供するため、IUCNが提案する信託が設立され、この地域の長期的な保全が支援される。DCPLとIUCNは現在、「ダムラ保全信託」の設立手続きを開始している。この信託は、オディシャ州の海岸線におけるウミガメの保護、代替生計を通じた生活の質の向上、女性のための機会の促進、村人のエンパワーメントに焦点を当てる。
より広範なスケールでは、このプロジェクトによって、民間、公共、市民社会の関係者の間で、優れた科学を用いれば、持続可能な方法で、開発と環境の両方に同時に取り組むことができるという理解が深まった。このプロジェクトの成果は、環境の持続可能性に関するビジネス側だけでなく、持続可能なビジネス慣行における同様のブレークスルーを可能にするために環境保護団体が果たすことのできる役割についても、認識を変えつつある。
受益者
- DPCL
- タタ・スチール
- IUCN(国際自然保護連合)
- 漁業者と地元コミュニティ
- オリーブミドリガメの個体数
持続可能な開発目標
ストーリー

ダムラ港の物語は、誤解、技術的な困難、対立の物語である。しかしそれはまた、決意を固めた個人、賢明な企業、革新的なアプローチ、そして相互利益の物語でもある。最終的には、オリーブの仲間であるウミガメとオディシャ州の人々にとってハッピーエンドとなった。
インドでは多くの環境保護団体が港の開発に反対した。タタ・スチールは、ウミガメに害を与えることなくインフラを建設できるかどうかを評価するため、IUCNに助言を求めた。
IUCNはウミガメの世界的な専門家を招き、同社と協力して緩和策を実施した。IUCN内の環境保護団体やNGOのメンバーは、IUCNの関与に批判的だった。彼らは、この脆弱な種の個体群に害を与えることなく港を建設することができるのか疑問に思ったのだ。
国際的な証拠によれば、標準的な作業手順に従えば、港とウミガメの共存は可能だった。国際的な専門家ネットワークを動員することで、IUCNは客観的な科学と保全へのコミットメントをもたらすことができた。
IUCN理事会が承認した「ビジネスと生物多様性戦略」では、「大きな足跡を残す」産業との協力が義務付けられているにもかかわらず、一部のIUCN会員は、IUCNは化石燃料を多用する特定の産業と関わるべきでないと感じていた。また、大規模な開発プロジェクトに影響を与え、生物種への影響を緩和できる可能性を考慮すれば、妥協する価値はあると主張する者もいた。
世界的なベストプラクティスに基づき、国際的な科学コミュニティはこの立場を支持し、環境破壊は緩和できると結論づけた。IUCNはプロジェクトにおいて中立的なパートナーであり続け、最適な結果を得るために科学を活用した。IUCNにとってこのプロジェクトは、自然と地域社会にとって最良の結果をもたらすためのビジネスとの関わり方について学ぶ重要な機会となった。
2つの組織は多くの困難を乗り越えて協力し、開発と自然保護が共存できること、人と自然のニーズを同時に満たす責任ある方法で開発する方法があることを示した。タタ・グループと国際自然保護連合(IUCN)の間に確立された信頼関係は、生物多様性保護が大きな足跡を残す産業の中核的な原則となり得ることを証明し、他の形での関与へとつながった。