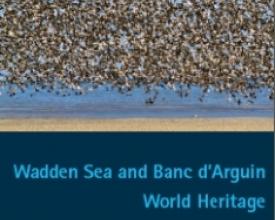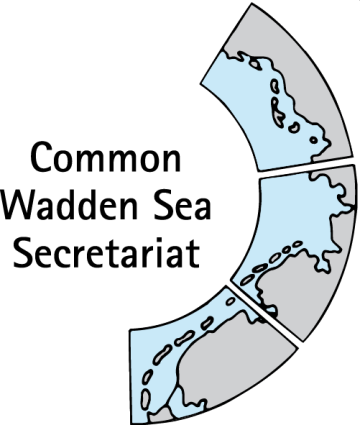干潟生態系保全のための東大西洋フライウェイ・パートナーシップ バンクダルギン - ワッデン海

ヨーロッパのワッデン海(DK、DE、NL)とモーリタニアのバンク・ダルギン国立公園(PNBA)は、アフリカ・ユーラシア・フライウェイの渡り鳥を通じて結ばれた2つの世界遺産であり、重要な越冬地および中継地として機能している。それ以来、管理者と科学者の二国間訪問、共同行動計画、鳥類モニタリングにおける協力が行われている。さらにPNBAは、東大西洋フライウェイ沿いの水鳥の保護と監視を強化するために発足した「ワッデン海フライウェイ・イニシアチブ」を共同で推進している。
コンテクスト
対処すべき課題
-
東大西洋フライウェイ沿いの渡り鳥に対する脅威とリスクに関する概要の欠如。
-
鳥の渡りや世界遺産の重要性に関する一般市民や政策立案者の認識が低い。
-
渡り鳥の個体群全体を監視するための、東大西洋フライウェイ沿 での統一されたデータ収集方法およびスケジュールがない。
-
保護区を管理する能力、知識、スキルの不足。
所在地
プロセス
プロセスの概要
すべての構成要素は絡み合っている:MoUは、協力のあらゆる側面における法的基盤である。共同コミュニケーションの努力により、政策立案者、一般市民、利害関係者に科学協力とノウハウの交換について情報を提供し、生物多様性にとっての両サイトの協力の重要性を示す。共同科学プロジェクトは、科学と研究、サイトの管理と保全の分野での協力を強化する。さらに、MoUを支援するステークホルダーのネットワークを構築し、コミュニケーションのためのインプットを生み出す。
ビルディング・ブロック
共同コミュニケーションと外観
渡り鳥とその生息地に関する情報を国内および国際レベルで発信し、その保護の重要性に対する認識を高めるための共同出演。例えば、ITBベルリン2017での渡り鳥に関する展示や共同チラシなどがある。
実現可能な要因
共通の課題と共同目標を定める。
教訓
共同コミュニケーションは、国際的により広範な認識を生み出す。
リソース
ノウハウの交換
専門家と現場管理者の定期的な交流訪問とノウハウの交換。これらの会議は、バンク・ダルギンとワッデン海の両方において、調和された価値観と方法を教え、実践する能力構築の手段である。共通のモニタリングと管理方法が調和され、知識と理解の共有レベルが構築される。参加者はそれぞれの保護地域の科学者、サイト管理者、その他の専門家である。
実現可能な要因
専門家と管理者の交換訪問は、日中韓ワッデン海協力機構と各国のパートナー(国立公園など)から資金援助を受けている。当初から、このMOUの地域レベルおよび国レベルのすべてのパートナーは、東大西洋フライウェイ沿いのWHの財産、特に渡り鳥の保護を強化する利点を理解していた。
教訓
文化の違いは、自然保護と管理に対する理解の違いにつながる。例えば、共通の目標と管理方法を定めるためには、自然保護に対する多様な見解を両サイトで認めなければならない。
科学協力
ワッデン海とバンクダルギンの自然資源の保全と管理を促進するための、渡り鳥の共同モニタリングプログラムと、共通の科学的・管理的プロジェクトの支援。この2つのサイトが、東大西洋フライウェイ全域に沿った同時集計を主導し、フライウェイを利用する渡り鳥の個体群状況の全体像を把握することが目標である。ワッデン海とバンクダルギンにおける渡り鳥の調査は、フライウェイに沿った他のすべての越冬地、繁殖地、中継地と密接に関連しており、重要な意味を持つ。したがって、科学的な協力によってのみ、フライウェイの全体的な認識と、管理を成功させるための共通の基盤を得ることができるのである。
実現可能な要因
リサーチ・クエスチョンと自然観察地の共通点を共有。
教訓
文化の違いは、モニタリングと科学的調査に対する理解の違いにつながる。例えば、科学的調査とモニタリングに対する異なるアプローチを検討し、共通の道を見つけるために議論しなければならなかった。
影響
2014年以来、MoUは干潟生態系の保全、管理、持続可能な利用の分野における知識と経験を共有する機会を提供してきた。世界規模で渡り鳥を管理・保全する必要性を理解するため、コミュニケーションと認識が強化された。研究活動への支援も得られた。MoUは、フライウェイ沿いの利害関係者や組織間の協力を促進・支援した。さらに、世界遺産条約の実施を支援してきた。
受益者
地元コミュニティ、バン・ダルガンの先住民、国立公園
ストーリー

フライウェイに沿った渡り鳥の効果的なモニタリングと保護は、そのルートに沿った多くの中継地のうちのひとつだけを見るのでは不可能であり、全体として見る必要がある。ワッデン海のユッタ・レイラー博士は、アフロ・シベリアアカノエボシ亜種に関する博士課程研究において、このような全体的なアプローチに従っている。これらの鳥は、最も重要な越冬地であるモーリタニアのバンク・ダルギンと、渡りの中心的な中継地であるワッデン海の両方に強く依存している。そこでレイラーは、2003年から2009年にかけてモーリタニアの国立公園を頻繁に訪れ、両方の場所を探検した。「この数年間で、私は持久力の重要性を学びました」とレイヤーは言う:「長期にわたって頻繁に現地を訪れることで、現地の人々と今日まで続く関係を築くことができました。モーリタニアの同僚たちにも、私がこの交流に全力を注いでいることを示すことができました」。
2014年から2015年にかけて、彼女はCIM国際移住センターの統合専門家としてモーリタニアに戻り、GIZと協力して管理体制の構築を支援した。同時に、ユネスコの要請を受け、日中韓ワッデン海協力機構とバンク・ダルギン国立公園は、覚書を締結し、より強力な協力関係を構築することを検討した。両地域とそのコミュニティをよく知るレイヤーは、2014年の覚書調印に向けた仲介役となり、不可欠なピースとなった。
「私の目には、覚書は何よりもまず、コミットメントを示しているように映ります:「関係国は、互恵的な協力関係を長期的に追求することに署名した。このような文書があることは、特に財政的な支援や長期的なスタッフのリソースが必要な場合、交流の実際的な側面に取り組む際に非常に役立ちます。これは、従来の短期的な開発プロジェクトにはない大きな利点です」。
現在、レイヤーはドイツNGO NABU(バードライフ・ドイツ)のミヒャエル・オットー研究所に勤務し、東大西洋フライウェイ沿いの水鳥保護とモニタリングの強化を目指すワッデン海フライウェイ・イニシアチブとのつながりを深めている。MoUは間違いなく最初の一歩であり、それに伴い、サイト管理者や研究者の交流が行われてきました。しかし、そのほとんどは、ワッデン海からバンク・ダルガンという一方向へのものでした。最終的には、モーリタニアの同僚たちが頻繁にワッデン海を訪れるようになるはずだ。それは私たちがまだ達成しなければならない目標だ。しかしMoUによって、私たちはそれを達成するための長期的展望を持つことができるのです」。