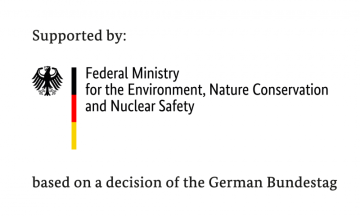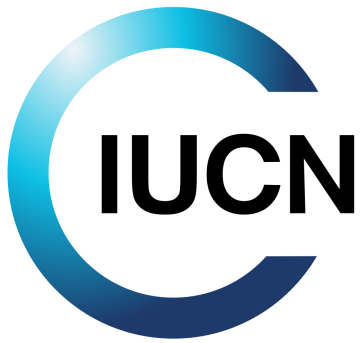
メコンデルタ上流における洪水を利用した農業

IUCNは、ベトナムのアンザン(An Giang)省、ドンタップ(Dong Thap)省、ロンアン(Long An)省において、地元で実践されている洪水を利用した(湿地)農業と生計モデルを推進し、改善しました。これらの実践は、文書化された農民の知識と経験に基づいています。洪水を利用した生計は、経済的に実行可能でリスクが低く、稲作3連作(主要な農業慣行)に代わるものとして奨励された。この方法は、経済的・気候的回復力を高めるだけでなく、メコンデルタの淡水湿地帯や氾濫原に見られる生物多様性の保全・回復にも役立ちます。介入は自然に基づく解決策を採用し、浮稲システム、蓮栽培システム、稲養殖システムという3つのシステムを検討した。さらに、異常気象が増加していることから、ハイブリッド型の解決策(堤防と氾濫原の組み合わせ)も検討された。ハイブリッド・モデルは、制御された洪水と適応的なアプローチを可能にし、干ばつのリスクを克服し、洪水の到来と後退を管理することで、より作付のニーズに合わせることができる。
コンテクスト
対処すべき課題
メコンデルタの氾濫原では、ポルダリングによる三毛作が主要な農業慣行となっている。この慣行は、デルタの季節的な氾濫原に著しい損失をもたらすとともに、土地の肥沃度の低下、洪水回復力の低下、水生生息地と生物多様性の減少など、生態系機能の低下をもたらした。洪水リスクの増大による悪影響は、ベトナムとカンボジアの国境を越えた課題ももたらした。こうした課題に対処するため、2013年のメコンデルタプランを皮切りに、自然ベースの解決策としての洪水を利用した農業というコンセプトが、より大規模な作業プログラムの一部として浮上し、その実現可能性を探る多くのプロジェクトが活用された。2015年から2018年にかけて、IUCNのパイロットサイトにおける農民のイニシアチブと概念実証の初期研究が完了した。これらは、この地域における同様のプロジェクト(世界銀行、IUCN、FAOなど)の設計と実施に反映された。
所在地
プロセス
プロセスの概要
ビルディング・ブロックは、ベトナムにおける洪水を利用した農業への介入を、IUCNネイチャー・ベースド・ソリューション世界基準(IUCN Global Standard for Nature-based Solutions)の基準と指標に照らして評価した結果、浮かび上がった多くの重要な洞察に焦点を当てたものである。同基準のすべての基準が同等に重要であるため、自然ベースのソリューションの全体像を示すものではないが、この新しい農業モデルの導入を成功させた要因のいくつかを示し、普及と規模拡大を進め、財政的な持続可能性を確保するための重要な次のステップを浮き彫りにしている。
ビルディング・ブロック
法的・政策的枠組みを軸とした介入の構築
自然に基づく解決策は、2013年のメコンデルタプランに基づくもので、洪水リスクを管理するために、季節的な洪水を利用した農業や養殖業と組み合わせた高価値の二毛作を推奨している。これは「持続可能で気候変動に強いメコンデルタのために」と題された国家決議120号の公布に影響を与えた。同決議は2017年11月に採択され、「積極的に洪水と共存する」ことを基本に、環境に優しく持続可能な開発を実現する自然ベースの適応モデルを選択すべきと規定している。さらに、毎年開催されるメコンデルタフォーラムでは、各国政府と開発パートナーが一堂に会する。このフォーラムは、より自然な土地と水の利用への移行を含む、メコンデルタ上流部の共通のビジョンについて、学んだ教訓や支持に関する知識交換の場を提供している。
実現可能な要因
2013年のメコンデルタプランは、さまざまな社会的課題と便益を捉え、洪水を利用した農業システムの実施を支援した。社会的課題には、ポルダリングによる集約的な稲作によるメコンデルタの氾濫原の喪失とそれによる洪水吸収能力の低下、土地の肥沃度と帯水層の涵養域の減少、水生生息地と生物多様性の減少、さらに害虫リスクの増加、漁業の損失、土砂と土壌の肥沃度を補うための投入コストの増大による社会経済的不平等の拡大が含まれる。
教訓
支援的な法的・政策的枠組みは、土地利用を変更する機会を開き、開放洪水・洪水調節区域で洪水を利用した農業を導入するための関連イニシアティブ間の連携を促進した。
様々なプロジェクト間の連携を強化し、規模に応じた影響力を高める
介入のデザインは、2013年のメコンデルタ計画にも盛り込まれた、メコンデルタ全域の課題を認識したものだった。自然に基づく解決策(Nature-based Solution)」は、他の同様のイニシアティブと協力しながら、知識のギャップ、農民の能力ニーズ、地域計画の課題に戦略的に取り組んだ。この介入策は、洪水を利用した農業を通じて生計を向上させるという観点から、環境と社会の相互作用に対応するものであった。IUCNの初期の試験的な介入は限定的で小規模なものにとどまったが、類似のプロジェクト間の協力や最近の政策動向は、現在、メコンデルタ上流部の氾濫原の140万ヘクタールにわたる大規模な介入の開発を支援している。
実現可能な要因
IUCNのパイロット事業から学んだ教訓や他の同様の取り組みから得た経験は、メコンデルタ開発パートナー作業部会や年次メコンデルタフォーラムで定期的に共有されている。さらに、洪水を利用した農業に対する学界からの新たな関心は、すでに関連するデータや情報を生み出し、協力やパートナーシップを強化している。
教訓
洪水を利用した農業と低堤防による洪水調節システムのハイブリッドシステムは、初期洪水や大洪水、干ばつのリスク管理に役立つ可能性がある。最も可能性が高いのは、季節的洪水時に水門を開いて洪水貯留域を回復させることによって、高い堤防を持つ閉鎖洪水区域である。しかし、既存のプロジェクトでは、この可能性にまだ取り組んでいない。このことは、ネイチャー・ベースド・ソリューションの介入が、規模に応じてプラスの影響を達成するためには、小規模(多くの場合、パイロット事業に焦点を当てる)でプロジェクト・ベースの期限付きの介入だけでは、複雑な社会的課題に取り組むには不十分であることを示している。とはいえ、この地域の関連する介入策間のパートナーシップは、制度や政策の発展に貢献し、セクターを超えた協調の強化を支援した。さらに、IUCNが主導する緑の気候基金(Green Climate Fund)の提案も準備中であり、取り込みを拡大し、取り組みの継続性を確保し、国境を越えた課題に取り組む。
洪水を利用した農業への移行のための資金援助
いくつかの費用便益分析から、異なる農業システム間の主なトレードオフに関する洞察が得られた。氾濫原の生態系サービスを保全・回復するための補償として、農民は洪水を利用した農業への移行のコストを賄うための支援を受け、さらに低堤防地域を洪水から土地を排除する高堤防による閉鎖的な管理区域に転換する圧力に対抗することができた。一部の地域では、低堤防で洪水が到達/後退するタイミングを制御し、二毛作や洪水を利用した作付け(伝統的な三毛作の稲作の代わり)を支援するハイブリッドモデルが用いられた。ハス農法の場合、洪水を利用した農業によって、魚の養殖、エコツーリズム、レクリエーションなど、活動の多様化が可能になった。
実現可能な要因
実施可能性調査の結果、季節的洪水を利用した農業が適用されれば、数十万人の農家と多くの下流の町が洪水から経済的な恩恵を受けることが明らかになった。さらに、洪水を利用した作物や作付けシステム全体の収益性について、米単作と比較した費用便益分析が実施された。
教訓
将来的には、新しい洪水ベースの農業モデルを支援し、コメ輸出業者からの支援を得るために、バリューチェーン、特にコメ生産について、より詳細に検討する必要がある。バリューチェーンを考慮することで、洪水に基づく生計モデルの経済的実現可能性が確保され、その導入のインセンティブとなる。協議や得られた教訓の分析を通じて、洪水を利用した農業を拡大するための最大の課題として、市場アクセスやバリューチェーン開発の不足が挙げられた。このことは、今後の緑の気候基金プロジェクトの設計においてすでに考慮されている。
影響
上流メコンデルタにおける洪水を利用した農業の採用がもたらす主なプラスの影響 には、氾濫原の生態系機能の強化による洪水リスク管理の改善などがある。洪水貯留能力の保全または回復により、帯水層の涵養、地盤沈下の軽減、水生生息地/生物多様性の保全または回復が実現した。さらに、野生漁業の可能性、季節的洪水による自然の水文学の再確立による河川浸食の緩和、季節的洪水による土砂堆積を含む土地の肥沃度の増加などのプラスの影響もある。
受益者
主に地元農家、政府代表
持続可能な開発目標
ストーリー

2016年には、メコンデルタの洪水保持戦略が提案され、これによって各省は氾濫原を横断してより協調的な方法で計画を立て、生態系を保護することができるようになった。洪水を利用した生計モデル、例えば蓮栽培、浮稲システム、稲作養殖などが、農民にとって経済的に実行可能な選択肢として戦略に盛り込まれている。
洪水を利用した農法への転換は、地元農家にとって多くの利点がある。集中的なハス栽培では、洪水水の貯水量の増加(1,000m²あたり約1,500m³)により、魚、カニ、水鳥の生息数が増加することがすでに実証されている。さらに、化学肥料や農薬を使用する必要もなくなった。
この自然ベースのソリューションの利点は、地元の農家も認めている:
タップムオイ郡ミホアコミューンの経験豊富な蓮農家、グエン・ゴック・ホン氏は言う:「堤防の高い地域の農民は、蓮の収益が稲作よりも高ければ、喜んで蓮栽培に転換すると思います。もちろん、ハス栽培は稲作よりも多くの水を蓄えることができる。そのため、より良い環境調整に役立ちます。ハスのモデルは洪水や干ばつにも対応できるので、気候変動の影響にも適応できると思います。ハスを植えることは、より高い収入をもたらすと同時に、環境にも優しいのです