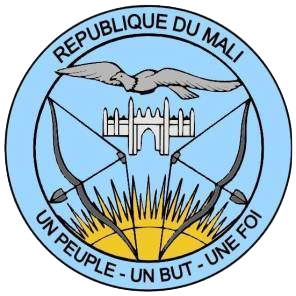地域が所有する自然資源管理による自然回復:生態系と社会の回復力への道

マリ・エレファント・プロジェクトは、42,000km2にわたる野生動物との共存という複雑な問題に、ランドスケープレベルの統合的アプローチを適用している。地元の関係者がゾウの存在に関連付ける複数の価値観に基づき、このプロジェクトは複数のレベルで同時に活動し、西アフリカに残された最後のゾウの個体群を保護するための解決策を共同で創造するために、関係者との参加型アプローチを用いている。人為的な生息地の喪失、環境悪化、紛争、密猟は、ゾウと地元の生活の両方を脅かしている。これらと闘うために、このプロジェクトはゾウの生息域の地域社会を支援し、自然生息地を保護し、環境劣化を回復させる地域社会中心の自然資源管理システムの確立を支援している。より健全な環境は地域の生計を支え、リスクのある若者に職業を提供し、特に女性には収入を得る機会を提供する。このようなシステムはまた、社会的結束を築き、ゾウの保護に対する地元の支持を強化する。
コンテクスト
対処すべき課題
- 過激派による無法、紛争、反乱
- 生息地の損失や生態系の劣化を防ぐことができず、自給自足の生活が困窮する地域社会
- 急増する家畜の群れや、遠く離れた都市中心部からのその他の商業的利益による乱開発
- 天然資源へのアクセスをめぐる氏族や民族間の社会的緊張の結果、集団的に尊重される管理システムが存在しない。
- プロジェクト地域は国際的な人身売買の主要ルートに面しているため、ゾウの密猟が発生している。
- 多くの野生生物種の消滅につながる無秩序な狩猟
- 武装集団が水飲み場を取り囲む密林を占拠し、ゾウが隠れ家から追い出され、職人による金採掘の影響と相まって、人間とゾウの紛争が増加している。
- 若者の失業と武装集団による徴用の脆弱性
- 若者や女性の経済的/社会的エンパワーメントの欠如
- ゾウの保護と保護区の管理に関する政府の能力不足
所在地
プロセス
プロセスの概要
すべての構成要素は密接に関連しており、最初の構成要素である「複雑性」の視点から派生している。この視点とは、問題をより広い文脈における人間同士、あるいは人間と自然との関係から生まれるものと捉えるものである。人間とゾウの平和的共存というビジョンに導かれ、慎重な行動によってポジティブな面を強化し、ネガティブな関係を解決する方法を見つける。すべてのステークホルダーの視点を尊重し、知識のギャップを埋め、「資産」と行動のための重要な介入ポイントを特定し、ネットワーク化するためには、オープンマインドが必要です。そのためには、利害関係者の間で共通の視点を共創することを促進し、草の根レベルで透明で公正な解決策を講じ、さらに新たな法律(例:新たなグルマ保護区)によって「可能にする」ことが必要である。利害関係者間の継続的な対話と学習が中心である。その波及効果は、純粋なゾウの保護にとどまらず、生態系と社会の回復力を向上させる原動力となっている。問題を広い視野でとらえ、社会的・生態学的エコシステム内の関係に焦点を当てることで、例えば、自然資源の保護や土地の修復に携わるリスクのある若者に職業を提供するなど、創造的な解決策を生み出す機会が増える。
ビルディング・ブロック
保全の課題に取り組むために複合システム・アプローチを適用することで、複数のSDGsを改善することができる。
どのような種も真空中では存在しない。直接的な生態環境をはるかに超えたレベルで、無数の相互作用する力が働いて、その運命を形作っている。このことを認識することは、種だけに焦点を当てるのではなく、その種が生きるシステム全体(生態学的、社会的、政治的、経済的)に目を向けることを意味する。また、「より広いシステムに同時に影響を与え、それによって形成される」(Canney, 2021)相互作用から生じる不確実性を受け入れることも意味する。つまり、先入観にとらわれた解決策では、本当に成功する可能性はほとんどないに等しいということだ。
何をすべきかわからないからこそ、プロジェクトは問いかけ、観察し、耳を傾け、その答えが文脈によって形作られるようにすることを余儀なくされた。長年にわたり、社会生態学的な背景を理解し、小さなインプットが比較的大きな影響をもたらしうる重要な介入ポイントを特定すること、「予期せぬ事態に対応し、機会を捉え、状況の変化に適応するための柔軟性を高める計画を立てること」(同書)、そして目的を達成するためにさまざまなレベルで、さまざまな利害関係者と協力することを意味してきた。当初はゾウに焦点が当てられていたが、このアプローチは事実上、複数の利益をもたらし、生態系の劣化から危うい生活、若者の失業、地方統治、社会紛争に至るまで、多くの問題を一度に改善することに貢献している。
実現可能な要因
複雑系理論を真に理解し、内面化することに時間をかけ、複雑な状況に適用したときに、単純で「制御可能」な解決策がいかに予期せぬ結果をもたらすかを見極める。
時間をかけて生態学的・社会的リテラシーを身につけること。
個々の実体や単純な因果関係ではなく、ネットワーク、つながり、力学に焦点を当てること。
より広い文脈の中で問題を研究するための準備期間。
型にはまらない(それゆえリスクの高い)保全のアプローチを支援しようとするホスト組織(WILD Foundation)の存在。
教訓
答えを持っていないことを覚悟し、何をすべきかわからないことを認める。
なぜそのような現象が起こるのかを問い続け、究極の原因を追求すること。
さまざまな分野、視点、個人からの理解を求め、それらがすべて部分的な解釈であることを認識すること。
すべての人を尊重し、たとえ自分に敵対する人であっても尊重する。
柔軟性を持ち、現地の状況に適応する。あるアプローチがうまくいかない場合は、その理由を追求し、解決策が見つかるまでトライし続ける。ダイナミックな環境では、解決策を継続的に見直す必要がある。
誰かに何かをさせたいのであれば、その行動を促すような状況を作り出すことで、強制執行にリソースを費やす必要がなくなる。
信頼関係を築くためには、自分の動機について透明で正直であること、そして一緒に働く人にも同じことを期待すること。純粋な動機から行動し、「青写真的な解決策」ではなく、現地の状況に導かれるようにする。
チーム内に複数の専門分野と補完的なスキルをバランスよく配置すること。この場合、ディレクターは自然科学出身で社会科学の経験もあり、フィールド・マネージャーは社会人類学者で自然科学をある程度理解している。
地域社会と利害関係者の参画とガバナンスに、真に共同創造的で地域に適応したアプローチを用いる。
このプロジェクトの地域社会との関わり方のアプローチは、常にまず耳を傾け、地域の問題や関心事を理解し、その中でゾウの問題を議論することである。あらゆる視点を認識し、問題に対する共通の視点を持つことが重要な第一歩である。問題のパラメータと共通のビジョンを特定することが次のステップである。そして、MEPを利害関係者として、解決策を考案するようコミュニティに求めることで、彼らの信頼を築き、オーナーシップを与え、持続可能性を育むのである。
それは、未知の部分が多く、柔軟性と学ぶ姿勢が必要であることを意味するが、現地の知識やノウハウに依存し、最初から参加者によって自動的に検証され、採用されるため、イニシアチブが成功する可能性が高くなることを意味する。
このプロセスには、コミューンの市長や政府の技術サービス機関の積極的な参加が必要であり、その役割は、地元のイニシアティブの実施や、コミューンの開発計画との統合において、コミュニティを支援することである。プロジェクトが実施されるためには、すべてのコミューンが自らのコミットメントを示さなければならない。これにより、すべてのステークホルダーが共に天然資源の管理に責任を持つことができるようになり、ローカル・ガバナンスが強化される。
実現可能な要因
マリの地方分権法では、天然資源の管理は地域コミュニティの手に委ねられている。
先入観にとらわれず、オープンマインドでこの問題に取り組み、現地の状況に応じて解決策を練り、地元コミュニティとのオープンな対話から生まれるようにすることが、信頼と協力関係を確立するための鍵となった。
現地の習慣や文化、そしてその微妙な違いを真に理解し、強力なファシリテーション・スキルを持つ現地出身のチームを結成したことは、このプロジェクトの最も強力な財産のひとつである。
教訓
これらの環境では、土地(生息地と生物多様性)の利用が重要な問題である。
このようなアプローチは、長期的な成功に不可欠なコミュニティの賛同と信頼を確実にする。
地元コミュニティがゾウの保護に反対するようなことになればと思うと気が重かったが、持続可能な解決策を考案するにはそれしかなかった。
地元のチームは、その地域出身で、その大義に情熱を持っていることが重要である。彼らは最も優秀な人材ではないかもしれないが、ファシリテーターとしての能力は、純粋なやる気と信頼とともに、成功のための重要な資質である。
それは、他の分野で彼らの能力を高めることを意味し、時間はかかるかもしれないが、他所から有能な人材を集め、地元での貢献をさらに根拠づけるよりはましである。
地元のファシリテーターを起用する理由はさらにある。また、極端な無法状態にもかかわらず、プロジェクトを継続することができた。
地元コミュニティは、失われた生態系と野生生物を回復させるという長期的なビジョンに興奮していた。
平和構築としての "象を中心とした "コミュニティベースの自然資源管理(CBNRM)。
防火帯を作る共同作業の後、火を囲んで食事をすると、みんな同じ問題を抱えていることに気づく」。
資源が限られている中で、しばしば対立する異なる生業(牧畜、農業)を受け入れるには、根底から対話する必要がある。このためプロジェクトは、ゾウの生息域に住む多様な氏族や民族が、共通の目標(この場合は天然資源の保護と生態系の再生)に向かって団結できるよう、ファシリテーターとしての役割を担っている。
コミュニティが一丸となって環境問題に取り組むことで、さまざまなレベルで恩恵を受けることができる。その結果、部分の総和よりも大きな、より強靭な解決策が生まれる。より健康的な生息環境、より豊富な天然資源、食料安全保障の向上と不利な出来事に直面したときの回復力、追加収入、女性や若者を含む社会的エンパワーメント、コミュニティ間およびコミュニティ内のより良い社会的結束、若者が「エコ・ガード」として地元で尊敬される職業を与えられることによる物理的安全保障の向上、彼らが移住したり武装集団に加わる可能性の低減、家庭やコミュニティに貢献し、自分たちの生活に対して何らかの主体性を発揮できることへの誇り、などがその恩恵に含まれる。
実現可能な要因
地元の人々のゾウに対する好意的な態度と、自分たちが同じ問題を共有しているという理解が、この活動を始めるための統一要素となった。
役割を求める失業中の若者たち、そして保護と修復を必要とする荒廃した生息地や土地。
教訓
人間と野生生物の対立は、その根底に人間同士の対立がある。そのため、例えば誰が得をして誰が損をするのか、力関係はどうなっているのかを理解することが重要である。
地元の失業中の若者は、家族や地域社会に貢献し、地元で尊敬される役割を求めている。これはお金よりも重要なことだ。したがって、彼らは大きな資源なのだ。彼らを参加させ、意味と目的を与えることは、強力な手段となりうる(例えば、武装集団によるリクルートに対抗する)。最初の報酬は、給与ではなく「認知」であってもよく、それは彼ら自身の努力のもとでさらなる発展を遂げるための手段となる。
コミュニティから個人を推薦してもらう前に、まずエコガードの役割について話し合い、求められる資質を明確にすることが重要である。
パートナーシップのネットワークを構築し、共通のビジョンのもとで利害を一致させる - 単独行動は禁物。
複合システム」アプローチを採用することは、ゾウの生息域にいるすべての利害関係者を、国内および国際的な遺産であるグルマゾウの保護という共通のビジョンのもとに結集させることを意味した。これは、それぞれの関係者(政府行政、技術サービス、観光産業、学校、プロジェクト、プログラム、地域で活動するNGO)が参加するワークショップを開催し、彼らの視点を理解し、インパクトのあるアウトリーチ資料や活動(学校プログラムを含む)をデザインすることを意味した。それはまた、国内の他の機関(外国大使館、MINUSMA、UNDPなど)の支援を取り込み、調整することも意味した。
国家レベルでは、政府と協力してゾウの管理計画を立案すること、森林管理官と軍の混成による密猟対策部隊を創設すること、チェンゲタW.から密猟対策の専門トレーナーを招聘すること、生物圏保護区モデルを用いてゾウの移動ルート全体をカバーする新しい保護区を創設することなどが含まれる。また、生物圏保護区モデルを用いて、ゾウの移動ルート全体をカバーする新たな保護区を創設する。マルチユース・ゾーンは地元のCBNRM条約によって管理され、必要に応じて森林管理者が補助的な取締りを行うことで、コミュニティ・システムを強化する。これにより、政府とコミュニティの利害が一致し、相互に強化され、保護区管理に費用対効果の高いアプローチが提供される。このトップダウン・アプローチは、コミュニティ参加というボトムアップ・アプローチを補完するものである。
実現可能な要因
ゾウをすべてのステークホルダーの統一要素として利用する
必要な現地情報を収集し、関係者を特定することができる現地パートナーを育成した。
プロジェクトを支援する関係省庁の要職にある人物を特定し、相互支援のために彼らを引き合わせたこと。
中核となる給与を支払うパートナー組織が、プロジェクトの資金調達と「離陸」を可能にした。
教訓
複数のパートナーと協力するのは時間がかかり、困難なことではあるが、すべての関係者がそのプロセスに利害関係を持ち、何らかの利益を得ることが期待されるため、結果ははるかに持続可能で弾力的なものとなる。
トレードオフの範囲は、当初の予想よりも大きかった。
特に政府の機能不全が著しい場合、政府関係者の関与を維持することは、継続的な努力を必要とするかもしれないが、国の能力とオーナーシップを構築するためには不可欠である。
重要な地位にある個人は、活動を大きく妨げたり、促進したりすることがある。例えば、妨害的な行動や不正行為が公になるような間接的な方法を見つけるなどして、その影響を制限する方法を見つけるために、「権力の風景」を理解しようとする複雑系アプローチを用いることができる。
保護地域と景観計画を支援するコミュニティ資源ガバナンス(トップダウン/ボトムアップの相乗効果)
MEP はマリの地方分権法を利用して、地元の人々とともに「ゾウを中心とした」CBNRM のモデルを構築した。この法律は、村やコミューンレベルでの資源管理のモデルを生み出す重要な機能を果たし、それは地方やコミューンの条約やコミューンの社会経済開発計画に明記された。MEPはその後、政府と協力してこれらのシステムをさらに強化するために、コミュニティ条約をサポートする生物圏モデルを用いて、ゾウの移動ルート全体をカバーする新しい保護区を創設する新しい法律を起草した。その目的は、政府の森林管理者に、必要に応じて地域社会の条約施行を支援できる権限を与え、地域社会のシステムを強化することであった。これにより、政府とコミュニティの利害が一致し、相互に強化され、保護区管理に費用対効果の高いアプローチが提供される。このトップダウン・アプローチは、コミュニティ参加というボトムアップ・アプローチを補完するものである。
実現可能な要因
象を中心とした」CBNRMのモデルが考案された。
教訓
草の根のエンパワーメントを促進するための法律の重要性。
コミュニティーのさまざまな部分をまとめる中立的な「促進」機関の必要性。
新しい法律を制定するプロセスのスピードは長く、政府のパートナーがどの程度関与し、イニシアチブを支持しているかに左右されるが、NGOは技術的支援を提供し、前進を促すことができる。
影響
このプロジェクトの統合的なランドスケープ・アプローチは、当初はゾウの保護に重点を置いていたが、その結果、いくつかのSDGsに貢献する複数の成果をもたらした。
コミュニティは、地域の生計の基盤である天然資源の管理に責任を持つことで、自分たちの福利を向上させる力を得たと感じている。これは彼らにオーナーシップを与えることになる。
"ゾウがいなくなるということは、環境が私たちにとって良いものでなくなるということだ"。
その結果、ゾウやその他の野生動物にとって、環境の回復と再生、健全で実行可能な生息地がもたらされた。
その他の利点としては、生計の向上、(コミューンや村レベルでの)地域統治、社会的結束、若者の職業、女性の機会、人間とゾウの紛争を解決する方法などがある。
これらすべてが環境と社会の回復力を高め、地域コミュニティとコミューン行政のゾウ保護への支持を強化し、これらの地域条約は関連する16のコミューンの社会・経済開発計画の不可欠な一部となっている。
政府との協力の結果、ゾウの管理計画が策定され、ゾウの生息域42,000km2をカバーする保護区が新たに設置され、その中にはゾウの駆除メカニズムも含まれています。また、マリ初の密猟対策部隊が設置され、コミュニティの信頼と支援に支えられてゾウの駆除を防ぐことができました。
受益者
主な受益者は、グルーマの地域社会とマリ政府である。国内および国際的な遺産として、象徴的なグルーマ象の保護は、マリ、西アフリカ、そして世界の人々にも利益をもたらしている。
持続可能な開発目標
ストーリー

2003年にMEPが開始されたとき、人間による圧力の増大は生息地の損失と劣化をもたらし、環境と社会の回復力を低下させ、生計を困窮させ、社会と人間とゾウの衝突を悪化させていた。
意識調査の結果、地元の人々はゾウの消滅を望んでいないことが明らかになった。彼らは、ゾウは健全な生態系の証であり、人間の活動は環境の限界を尊重しなければならないことを理解していた。さらに調査や協議を重ねることで、根本的な要因、コミュニティの問題、価値観、ゾウとの関係などが明らかになった。無秩序な天然資源利用が核心であり、個々のグループはそれに対抗する行動をとることができなかった。つまり、マリの地方分権法は、人々とゾウの利益のために自然資源の回復と持続可能な利用を可能にする資源管理システムに関して、多様な地域グループ間の合意形成を助ける適切なツールだったのです。
この「ゾウを中心とした」CBNRMシステムには、コミュニティの仕組みを作ることが含まれていた。それは、各コミュニティによって選ばれた、若い非武装のコミュニティエコガードによってサポートされる長老からなる委員会であり、パトロールやコミュニティ協定の執行、資源保護や回復活動の実施、地域意識の向上などを行う。
コミュニティの規則は、資源(水、牧草地、森林、野生生物)を乱用から守り、保護林と牧草地の保護区を宣言し、エコガードたちが築いた防火帯で保護した。その年、乾季が進んで火災が発生しても、彼らの牧草地は生き残った。乾季の終わりには家畜のための牧草地が十分に確保され、干し草や放牧地を他の農家に高値で売ることができた。彼女たちの牛は市場で50%以上の価値があり、若く、病気も少なかった。女性たちは、干草や飼料、アラビアゴムなどの林産物の販売など、天然資源の利用を基盤とした地域事業を立ち上げることができた。こうした活動はコミュニティ内の調和を促進し、民族間の緊張を和らげることにもつながった。
コミュニティのルールには利益の分配も含まれていたため、ゾウの保護に対する地元の支持はより強固なものとなった。紛争や無法地帯の出現に伴ってゾウの密猟が現れると、コミュニティのエコガードはゾウや密猟、HECを監視した。2015年に密猟がエスカレートしたとき、彼らは政府に密猟対策の支援を要請した。MEPは政府と協力し、グルマの密猟対策部隊を創設し、生物圏保護区モデルを用いてゾウの生息域に新たな保護区を設定した。