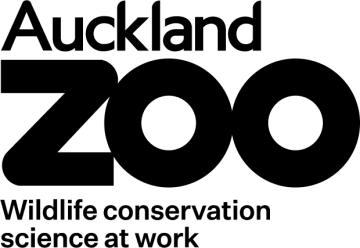ベリンジャー・リバー・ウイルス病への対応

2015年、生息域が非常に限定されているベリンジャー・リバー・スナッピング・タートル(Myuchelys georgesi)が大量死する事件が発生し、6週間足らずで種の90%が絶滅した。初期緊急対応として、現場調査、死体や病気の動物の除去、水質調査などが行われた。最終的にベリンジャー・リバー・ウイルス(以前は未知のウイルス)が原因であることが判明した。この大量死事件の背景をより深く理解するため、動物、原因物質、周辺環境が互いにどのように影響し合っているのか、ワンヘルス・アプローチがとられた。IUCN SSC/OIEの野生動物疾病リスク分析プロセス(Jakob-Hoff et al, 2014)を取り入れたマルチステークホルダーによる保護計画ワークショップが開催された。これにより、ベリンジャー・リバー・ウイルスの発生に関連するすべての潜在的要因が、当面の、そして長期的な優先順位と現場での回復行動に反映されることが確認された。
コンテクスト
対処すべき課題
死亡事故後、保護計画担当者が直面した主な課題は、死因が不明確であることと、この種の個体数が少ないことだった。ベリンジャー・リバー・スナッピング・ガメは、ベリンジャー川の推定80kmの区間に生息する固有種である。2015年以前、野生の個体数はおよそ4,000頭で、この種は今回の大規模な死亡事故により絶滅の危機に瀕している。さらに、ベリンジャー・リバー・ウイルスは成体のカメの個体群に不釣り合いな影響を与えた。繁殖の生態上、この種の再繁殖能力は急激に低下した。緊急対応の初期段階では死因がわからなかったため、広範な調査が行われ、最終的にこれまで知られていなかったベリンジャー・リバー・ウイルスが特定された。
所在地
プロセス
プロセスの概要
オープンかつ誠実な協力関係によってのみ、人工飼育と人工 飼育というこれまで縦割りであった部門を効果的に統合することができるのです。生息地の調査、現状調査、疾病リスク分析、飼育下繁殖プログラム、再導入プログラムなど、完全な対応は政府当局が主導したが、多様な利害関係者によって支えられた。開発されたパートナーシップは、このユニークで絶滅の危機に瀕した種を保護したいという共通の願いに根ざしたものであり、永続的なレベルの協力と情報共有を可能にした。
ビルディング・ブロック
ワン・プラン・アプローチ
IUCN CPSG によって開発されたワン・プラン・アプローチ(OPA)は、その種の域内個体群と域外個体 群の両方に関わるすべての利害関係者の意見を取り入れて保全計画を策定する種管理の方法である。これには保全管理者、すなわち野外の生物学者、研究者、野生個体群を監視する野生生物 管理者、さまざまな域外の個体群を管理する動物園や水族館の職員が参加します。専門家、研究者、意思決定者、利害関係者の代表が、中立的な CPSG の進行役が主催するワークショップに集められ、種の状態のレビュー、病気のリスク分析を行い、保全管理計画を策定しました。
実現可能な要因
ワン・プラン・アプローチ(OPA)は、絶滅危惧種にとって最善の利益となるよう、複数の利害関係者による合意決定を求める協調的な保全計画プロセスである。 種と疾病リスクに関する最も関連性の高い情報は、ワークショップの前に収集され、共有された。CPSGのファシリテーターはお互いを尊重し、協力し合える環境を作ることで、ワークショップ参加者が効果的に働き、種のための統合的な短期・長期計画を策定することを可能にした。
教訓
CPSGが40年以上にわたって培ってきた保全計画の原則と手順は、2015年の大量死亡事故後、ベリンジャー・リバー・スナッピング・タートルの保全に向けたワン・プラン・アプローチを成功に導いた。システムベースのワンヘルスレンズ(動物、人間、環境の健康の相互作用を包含する)を通して課題に取り組むことで、カメが直面する広範な脅威を捉え、緩和戦略を策定する計画が策定された。プロセスの初期段階から多様で関連性の高い利害関係者を参加させたことで、計画は最新の知識に基づき、広く受け入れられ、実施されることになった。
協力的パートナーシップ
カメの死骸の最初の発見から、最終的に飼育下で繁殖させた幼生を野生に戻すまでの大量死事件への対応プロセスは、政府当局、研究者、人工飼育・域外保全管理者、そしてカメの健康に個人的に投資している地元の人々の協力によって行われた。ベリンジャー・リバー周辺に住むコミュニティは、自分たちの世界の片隅に生息する固有種に誇りを持っており、彼らの関心と市民科学者としての参加は、意識を高め、資源を確実にカメに向ける上で大きな役割を果たした。政府当局は、包括的な分析が確実に行われるよう、さまざまな分野の専門家を探し、対応の中心的な推進役となった。
実現可能な要因
CPSGの原則である中立的なファシリテーションは、保全の課題に取り組むための協力的でオープンマインドな場を作り出す。この対応とワークショップに参加したステークホルダーは、それぞれ異なるセクターの出身で、それぞれの動機を持っていたが、ベリンジャー・リバー・スナッピング・タートルが直面しているすべてのリスクに対処する保護計画を策定するという統一された最終目標が、そうした違いを埋めることができた。
教訓
自然保護計画は、その根拠となる情報によって制限されることが多い。より広範なステークホルダーと関わることで、これまで考慮されていなかった多様な視点を計画プロセスに取り入れることができる。これにより、あらゆるリスクが考慮され、より包括的で充実した管理計画と、野生での長期的な生存のための包括的な基盤が生み出される。
影響
ベリンジャー・リバー・スナッピング・タートルの小規模な固有個体群が絶滅するのを防いだのは、大量死事件に対する複数の機関による包括的な対応だった。タロンガ動物園を通じて飼育下繁殖プログラムが対策の初期段階で確立され、それ以来、80頭以上の幼ガメが協調的な回復プログラムを通じて川への放流に成功している。個体群強化は、複数の補完的な調査や現場での行動とともに、IUCN-SSCの保全計画専門家グループ(CPSG)がファシリテートして策定した保全計画の重要な要素である。保全計画策定におけるマルチステークホルダーによる協力的なアプローチにより、疾病の緩和策、河川生態系が直面する脅威への対応策、継続的なモニタリングに地元コミュニティを参加させる方法などを盛り込んだ、コンセンサスに基づく管理計画が策定された。この病気によってベリンジャー・リバー・スナッピング・タートルは絶滅危惧種に指定されたものの、現在では継続的な管理によって野生種の存続が期待されている。
受益者
- ベリンジャー・リバー・タートル
- 大河川の生態系
- 自然保護計画立案者 - 政府および研究者
- ベリンジャー川周辺の地域社会
持続可能な開発目標
ストーリー

2015年、ベリンジャー・リバーの川岸に流れ着いたカメの死骸や瀕死の報告が、自然保護科学者、野生生物管理者、獣医師、そして結束の固いベリンゲン・コミュニティに衝撃を与えた。より多くのカメの死が報告され、病気のカメを治療しようという初期の試みが効果的でなかったことが判明するにつれ、災害の規模が明らかになった。原因不明の大量死が、ベリンジャー・リバー・スナッピング・タートルの小規模な固有個体群を急速に絶滅させたのだ。初期の調査では、汚染や毒性が原因である可能性は否定され、緊急救助隊はすぐに野生生物の病気が原因である可能性が高いという結論に達した。保護管理者と科学者は事故対策チームや地元コミュニティと迅速に協力し、健康な個体が生息していると思われる川の上流域を特定した。緊急捕獲が計画され、保険集団の確立を目指した。病気のウミガメが最初に報告されてから数週間も経たないうちに、チームは緊急にウミガメを捕獲した。地域住民の厳しい監視と期待、そして知りたい、説明を受けたいというニーズがあった。ベリンジャー・リバーはベリンゲン・コミュニティの中心であり、カメの窮状は多くの人々の関心事だった。健全な保険集団の収集は、緊急性と不確実性のバランスを取る必要があった。捕獲と集水域外への輸送には厳格なバイオセキュリティガイドラインが設けられ、ウェスタン・シドニー大学に検疫施設が建設された。病気が進行する前に、川の上流から17匹の健康なカメが回収された。これらの個体は現在、飼育下繁殖個体群の基礎となっており、2018年以降、80匹以上の子孫がベリンジャー・リバーに放流されている。今日、ベリンジャー・リバー・スナッピング・タートル・プログラムは確立された保護回復プログラムであり、その成功は幅広い人々の献身と協力のおかげである。ボランティアは年2回の調査と水質モニタリングを支援し、50を超える私有地所有者が河川生息地への立ち入りを許可している。このプログラムを率いる政府チームは、ウミガメの回復に取り組むことは特権であり、野生種の回復という共通の目標に貢献しているすべての人々に感謝している。緊急対応や初期の保護計画で築かれた強力な協力関係や永続的なパートナーシップは、このカメの回復において重要な強みであり続けている。