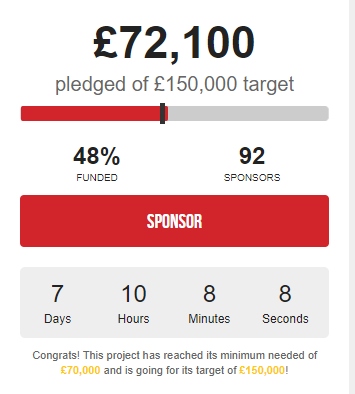ファンダーのピッチ・パックのデザイン&プロジェクトの立ち上げ
6月5日、セーシェルで打ち上げ。アルダブラ清掃プロジェクト・ボランティアの選考
State House Office of the President of the Republic of Seychelles.
6月5日、セーシェルで打ち上げ。SIF理事がセーシェル大統領にアルダブラの地図を贈呈。
State House Office of the President of the Republic of Seychelles.
6月5日、セーシェルで打ち上げ。セーシェル大統領にアルダブラの地図を贈るSIFのCEOフラウケ・フライシャー・ドグレー博士
State House Office of the President of the Republic of Seychelles.
6月5日、セイシェルで打ち上げ。プロジェクトオフィサー兼共同チームリーダーのジェレミー・ラグアインがイベントを記録。
State House Office of the President of the Republic of Seychelles.
6月5日、セイシェル発表会。賓客が見守る。
State House Office of the President of the Republic of Seychelles.
6月5日、セーシェルで打ち上げ。大統領とゲスト、ボランティアとゲスト。
State House Office of the President of the Republic of Seychelles.
5月22日の英国ローンチ。ACUPのバナーを掲げるボランティアたち。
Adam Mitchell.
5月22日の英国ローンチ。ACUP共同チームリーダー、エイプリル・バートとオックスフォードの研究者。
Adam Mitchell.
5月22日の英国発表会。駐英セーシェル高等弁務官と談笑。
Adam Mitchell.
5月22日の英国ローンチ。ゲストと話し合うボランティアたち。
Adam Mitchell.
5月22日英国ローンチ。共同チームリーダーのエイプリル・バートがゲストにACUPを紹介。
Adam Mitchell.
5月22日英国ローンチ。ACUPのプレゼンテーションを見るゲストたち。
Adam Mitchell.
プロフェッショナルで、プロジェクトの重要性と予算を明確に示す、強力で簡潔かつ魅力的なピッチ・パックを作成することが必要です。プロジェクトに資金を提供することで、組織や企業がどのような恩恵を受けるかを明確にアピールすることが非常に重要です。例えば、○○万円で、資金提供者のロゴをプロジェクトのTシャツに使用し、すべてのメディア報道で資金提供者を言及する。 ピッチ・パックには、プロジェクトのロゴを含め、視覚的な資料を使用してポイントを伝える。このケースでは、アルダブラとその野生生物、そしてプラスチック汚染の影響の画像を使いました。イギリスとセーシェルでこのパックを配布するため、通貨換算や著名人の名言の使用など、現地の状況を念頭に置いて各パックを作成することが重要でした。ピッチ・パックと並行して、強いイメージとナレーションを使って問題と解決策を紹介するキャンペーン・ビデオも作成しました。これらのステップを経て、私たちはプロジェクトの立ち上げを計画しました。立ち上げの目的は、最大限のメディア報道を集め、対面イベントを通じてできるだけ多くの個人や企業に参加してもらうことでした。そこで私たちは、英国とセーシェルの両方でイベントを開催し、潜在的な寄付者や支援者を招待した。
ビジュアル・デザインに長けたチーム・メンバーは、ピッチ・パックがプロフェッショナルであることを保証する鍵となった。キャンペーン・ビデオでは、基本的なビデオ編集スキル、現場の映像、プラスチック汚染の影響などが必要だった。パックのデザインや企業へのアプローチ方法については、資金調達の専門家からのアドバイスが役に立った。ACUPの立ち上げは、ロンドン王立協会本部とセーシェル州庁舎という著名な場所で行われた。SIFの後援者であるセーシェル大統領ダニー・フォーレ氏は、ACUPを国家的意義のあるプロジェクトとするビデオスピーチを行った。
私たちのプロジェクトを売り込むのに最も成功しやすいのは、プロジェクトのチームメンバーや、セーシェルやアルダブラに関心を持つプロジェクト自体と何らかのつながりがある企業であることがわかりました。企業にEメールを送る場合は、あなたのリクエストに対応する適切な担当者にEメールを送るよう、時間をかけることが重要です。また、プロジェクトの目的や成果に関して誤解がないように、立ち上げイベント中にできるだけ多くの人と顔を合わせ、プロジェクトに関する質問に答えることは非常に良いアイデアです。また、すでにスポンサーシップがあれば、資金提供者の注目を集めやすくなりますし、地元や海外の通信社など、プロジェクトのメディア・パートナーがいればなお良いでしょう。