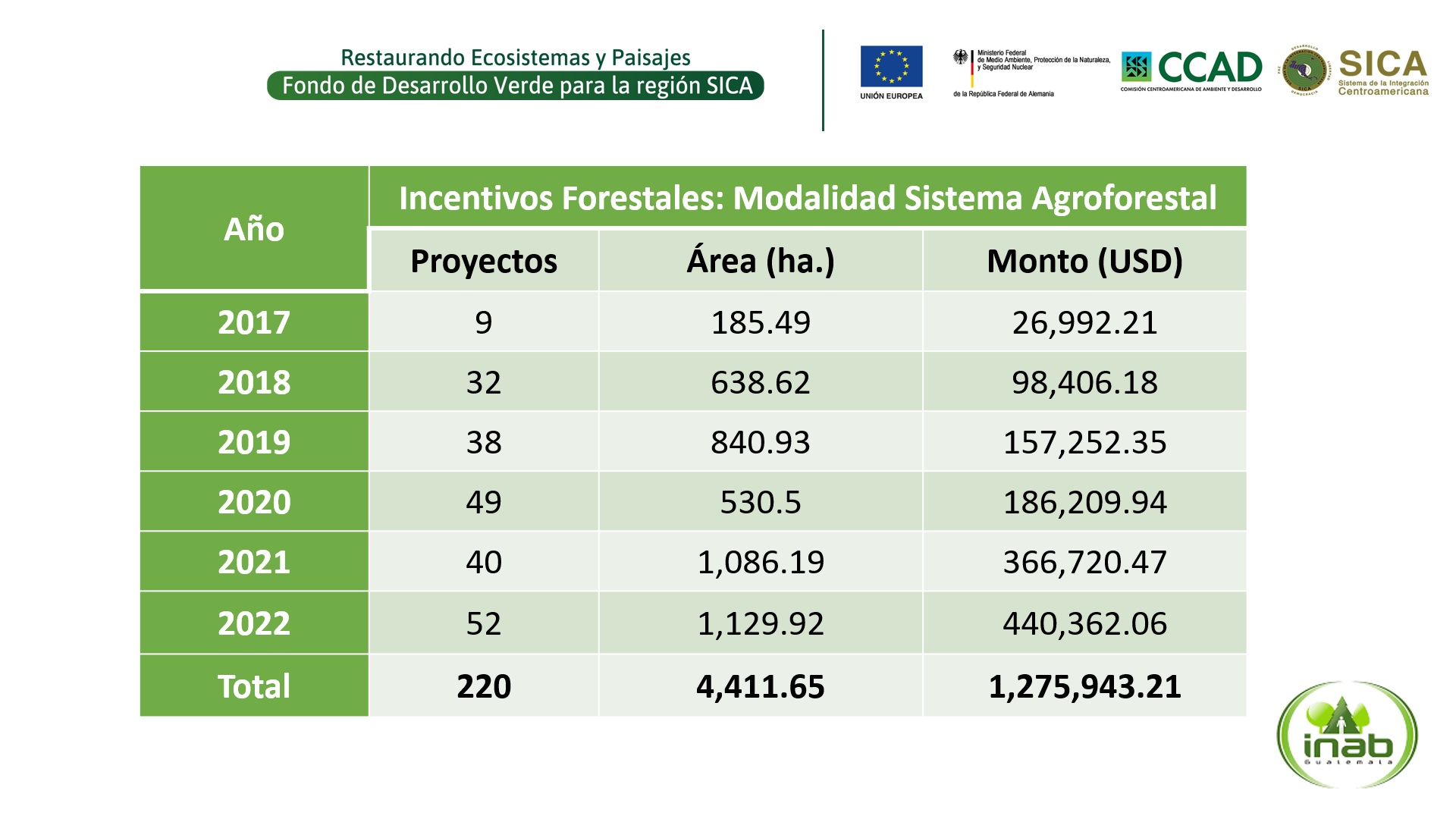このビルディングブロックの目的は、生態系や景観の修復プロジェクトの開発者や実施者に、現場での修復介入の有効性を評価する方法として、リモートセンシング、補強要因、およびこの2つの統合を使用するツールを提供することである。
リモートセンシングによる生態系サービスのインパクトラインを評価するために、ベースラインデータ(ベースライン、管理単位、最近の画像)を収集し、増分テーブルを定義し、画像を正規化・調整し、生態系サービスをモデル化することによって、初年度と最終年度の差分を計算する。
増分係数アプローチは、衛星画像から得られるスペクトル指標では植生変化を正確に検出できない農地や家畜に用いられ、ベースラインデータの定義、修復手法の分類、実施された対策ごとの増分係数の推定を通じて算出される。
このプロセスを実行することで、直接的・間接的に影響を受けた面積を知ることができる。