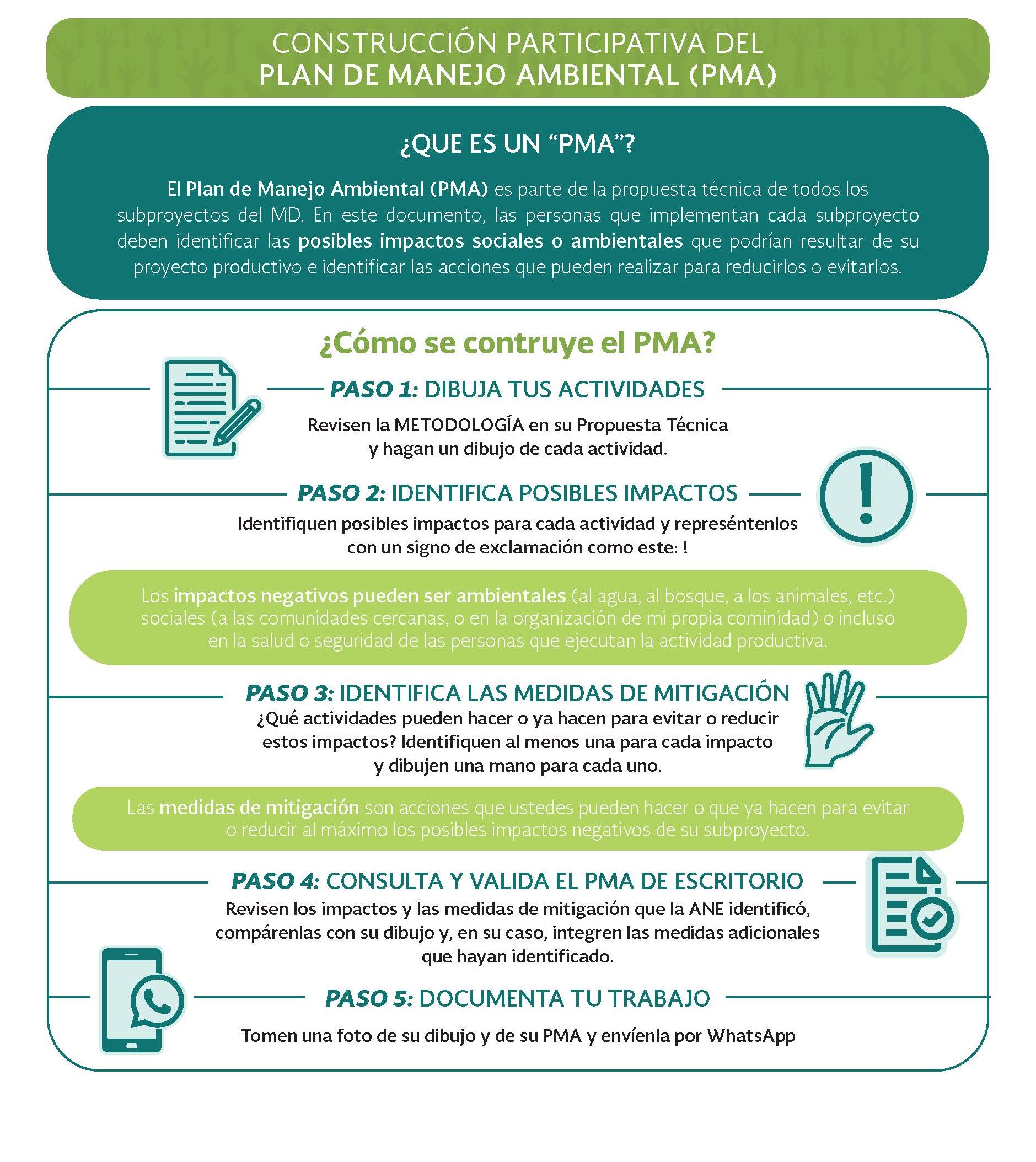マトンドニ村でのパイロットの成功に続き、近隣の村や組織が支援を求めるなど、ICSの需要は高く、受け入れられている。拡大努力の一環として、パテ小学校を含むパテ村に41台の調理用ストーブが建設され、さらに13人の研修生が参加した。
さらに、ラム郡政府はウェットランド・インターナショナルと提携し、試験的に5つの区に10台の調理用ストーブを設置しました。この取り組みは、同郡の総合開発計画2023-2027に沿ったもので、エネルギー効率を高める調理用コンロの重要性を強調している。ラムでは、合計3,010人がこれらの調理用ストーブの恩恵を受け続けている。