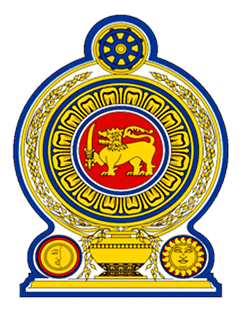環境的に敏感な地域保全、開発、回復力の物語

スリランカは国土こそ小さいが、その豊かな生物多様性と、生息地の侵食、持続不可能な資源利用、汚染、外来種による脅威の増大により、世界的な生物多様性ホットスポットの一部となっている。国土の28%が保護地域(PA)に覆われているが、重要な生態系の多くは保護地域外に存在する。このことを認識し、環境省とUNDPは、GEFからの資金提供を受けて、正式な保護区の外にある生物多様性と生態系サービスの価値が高い環境上敏感な地域(ESAs)の景観において、共同管理アプローチを実施した。このアプローチでは、官民セクターと地域コミュニティが参加し、生物多様性を保全すると同時に、周辺住民にとって不可欠な生態学的・社会経済的便益を維持している。包括的で持続可能な管理方法を推進し、保全と責任ある資源利用のバランスをとり、コミュニティと政府との協力協定を可能にした。このアプローチは、スリランカ固有の生物多様性を保護するために不可欠である。
コンテクスト
対処すべき課題
生物多様性を脅かす主な課題には、チェナ栽培のための森林伐採、単作などの持続不可能な農業、農薬の過剰使用、汚染、生物多様性の価値に対する認識の低さなどがある。農業生産性の低さは土地の侵食につながり、バリューチェーンや市場アクセスの貧弱さによる農業や観光業からの収入の低迷、男女間の賃金格差などの社会的問題を引き起こしている。環境ガバナンスの能力不足は、コミュニティと政府機関の間に不信感を生む。気候変動は、干ばつや洪水、気温の極端な変化の頻度や深刻さを増し、土地や森林の劣化、淡水不足、生物多様性の損失を加速させることで、こうした脅威をさらに強めている。こうした影響は、生態系サービスや伝統的な生計を、特に社会的弱者のために侵食する。根本的な原因としては、セクター間の制度的な連携の弱さ、生物多様性に配慮した計画の欠如、保全に対する公的・政治的コミットメントの不十分さなどが挙げられる。
所在地
プロセス
プロセスの概要
共同管理計画策定プロセスの3つの構成要素は、生物多様性アセスメント、脅威と傾向のアセスメント、参加型プランニング であり、 、相互に関連し、補強し合っている。生物多様性アセスメントは、何が保護され、なぜそれが重要なのかを理解するために必要な、基礎となる生態学的知識を提供するものである。このベースラインを基に、脅威と傾向のアセスメントは、生物多様性に作用する圧力を特定し、それらがどのように変化するかを予測する。これら2つのエビデンスに基づくレイヤーは、参加型プランニングに直接反映され、コミュニティや利害関係者が科学的知見を活用して、地元に根ざした実践的な管理戦略を設計する。参加型プランニングのプロセスは、オーナーシップを強化し、行動の実施可能性を高め、保全対策が社会的に受け入れられ、生計に沿ったものであることを保証する。これら3つの要素が組み合わさることで、科学が計画に反映され、計画が脅威に対応し、コミュニティが関与することで持続可能性が確保されるという、継続的なフィードバックシステムが構築される。
ビルディング・ブロック
共同経営アプローチ
森林、漁業、ESAなどの天然資源の管理について、地域コミュニティと当局が責任と意思決定を共有する協調的アプローチは、保全とコミュニティのニーズのバランスをとり、コンプライアンスを改善し、信頼を築き、長期的な持続可能性を確保するのに役立つ。
試験的ESAのひとつであるウェワルケレには、タンバラヤ(Labeo lankae)、ヒョウ、フィッシングキャット、ゾウ、ユーラシアカワウソなど、絶滅危惧種が生息している。125種の植物相のうち、背が高く密生したサトウキビ(Calamus)は、ぬかるんだ茨の木立に生えている。周辺の村々は手工芸品用にヒーン・ウェワルを収穫しているが、その多くは持続不可能な方法で収入を補っている。
ウェワルケレの生物多様性の価値と新たな脅威を認識し、部門事務局とコミュニティは2018年に地域管理委員会(LMC)を結成し、共同管理計画を策定した。この地域は、侵入を防ぎ、保全目標を確実にするために、社会調査を行い、物理的に区画された。
誰も置き去りにしないために、プロジェクトはコミュニティが非持続的な収穫から環境に優しい仕事へとシフトするのを支援した。長期的な生計を確保するため、サトウキビの苗床と植え替え施設も設立された。地方自治体、コミュニティ、LMCの強力なパートナーシップが、ESAの成功を確実にした。ウェワルケレは、コミュニティ、生息地、生物多様性が共存し、繁栄できることを示している。
実現可能な要因
1.明確な法的・政策的枠組み
2.強力な地方制度とリーダーシップ
3.信頼と効果的なコミュニケーション
4.公平な利益配分
5.キャパシティビルディング
6.一貫した政府支援
7.適応的管理とモニタリング
教訓
学んだ重要な教訓のひとつは、共同管理のための法的・政策的枠組みが存在しない、あるいは曖昧であることが、プロジェクトの初期段階におけるESAの介入の効果と持続可能性を制限してきたということである。明確で認知された後ろ盾が形成されれば、コミュニティの役割はより尊重され、権利は定義され、保全の成果はより永続的なものとなる......。
ESAの共同管理を成功させるためには、公平な利益配分が不可欠である。ウェワルケレESAでは、特にサトウキビを使った手工芸品産業を強化することで、保全活動が地元の生計と一致するように設計された。研修、市場との連携、制度的支援を通じて、生物多様性の保全に積極的に貢献しながら、コミュニティは安定した収入を得ることができた。コミュニティがESA管理の責任と報酬の両方を分かち合うことで、保全活動がより包括的、参加型、持続可能なものになることを、この相互利益的な取り決めが実証している。
リソース
伝統的知識の再発見と実践
これは、カスケード生態系とその周辺における生物多様性の持続可能な利用と保全を歴史的に支えてきた、先住民や地域の知識体系を復活させ、保存し、活用するためである。これらの知識体系は、何世紀にもわたる生態系との相互作用に深く根ざしており、生態系のバランスを維持する方法で天然資源を管理するための、実践的で時間をかけた方法を提供している。こうした知識を現代の保全科学と融合させることで、生物多様性への取り組みは、より文化的に尊重され、包括的で効果的なものとなる。スリランカタンク・カスケード・システム(エランガワ)は、水生生物多様性と乾燥地帯での稲作を支える古代の水管理手法である。
- 村の長老や伝統的な灌漑管理者(Vel Vidane)は、決まったカレンダーではなく、モンスーンの雨のタイミングやパターンに基づいて水門を開閉する時期を知っていた。彼らは、渡り鳥の初鳴きや樹木の開花、土壌層の水分といった微妙な兆候を頼りに放水を決定するのだが、これは工学的なマニュアルではなく、観察に根ざした実践である。
- 農民たちは伝統的に、塩分をろ過し、水質を保護し、土壌の健康を維持するために、タンクの下流端に植生緩衝地帯(Kattakaduwa)を設けている。この慣行は過去には科学的に説明されていなかったが、地元コミュニティはこの植生帯を取り除くと作物や水質に悪影響を及ぼすことを知っていた。
- 地元の農民たちは、土砂が沈殿する場所、定期的な浚渫の方法、土壌肥沃度を向上させるためにシルトを再利用する方法について、直感的に理解している。このような慣行は、正式な水文学的モデルがなくても、何世紀にもわたって水槽の維持に役立ってきた。
- コミュニティは、水槽やその周辺に鳥や魚、爬虫類が生息していることを生態系の健全性の一部として理解しており、正式な規則がなくても、営巣地を乱すことを避けたり、産卵期が終わってからしか魚を捕らない人さえいる。
実現可能な要因
- 地域社会の記憶と利用の継続性
- 文化的・宗教的意義
- 法的・制度的承認
- 科学的検証とパートナーシップ
- コミュニティ組織と農民組合
- NGOおよびドナーからの支援
- 世界的認知(GIAHSステータスなど)
教訓
- タンク・カスケード・システムを復活させたプロジェクトは、農民組合と国家機関の役割が協定で正式に取り決められたり、地元の政策によって支援されたりしている場合に成功しやすかった。正式な認識がない場合、コミュニティの努力はプロジェクトの資金提供終了後に崩壊することもあった。
影響
このソリューションは、周辺コミュニティの持続可能な経済発展を損なうことなく、生物多様性に配慮した環境を確立した。地元コミュニティと利害関係者が共同で保全指向の介入策を設計し、推進できるようにすることで、強い所有意識が育まれるとともに、経済的利益が保全のインセンティブとなった。環境上敏感な地域(ESA)管理アプローチは、生物多様性保全と統合的土地利用計画のための全体的モデルを、関係政府機関間で推進した。プロジェクトは、23,253ヘクタールをESAとして特定・管理し、23,763ヘクタールで生物多様性に適合した生産方法を導入し、183,957ヘクタールの保護地域をより広範な景観・海景管理計画に統合した。また、森林、カスケード・タンク、沿岸生態系、保護区外の孤立した丘陵地など、多様な生息環境の18,439ヘクタールで、ESA管理モデルのパイロットテストを実施した。これにより、ESAの運用に必要なガバナンスの枠組みが確立され、マナワカンダ、カラ・オヤ・リバーライン、ガンゲワディヤ、ヴィル、ウェワカレのパイロットサイトで、強力な利害関係者の協力が促進された。これらのモデルに基づいて、環境省は、保護地域外で生物多様性を保全しながら、持続可能で包括的な開発を可能にするための国家ESA政策を策定し、閣議で承認された。
受益者
- 地域コミュニティ、水稲およびその他の作物栽培農家(男女とも)、農民組織、地元農業関連企業
- 森林局、野生生物局、農務局、地方事務局などの地方政府機関
グローバル生物多様性フレームワーク(GBF)
持続可能な開発目標
ストーリー
スリランカのアヌラーダプラ県ガルネワ郊外にあるハバラワッテ村は、乾燥地帯に分類されているにもかかわらず、予想外に緑豊かな風景が広がっている。エメラルド色の水田が広がり、ミーやクンブクのような木々が群生し、村の貯水池がきらめき、田園風景の静けさを作り出している。
この静けさは最近のことだ。ほんの数年前まで、ハバラワッテは深刻な乾燥に苦しみ、村人たちは土地を耕すのに苦労していた。この変化は、州灌漑局が支援したコミュニティ主導の取り組みの結果である。この取り組みは、古くから行われてきた生態学的な慣習であるカスケード・タンク-村落システム(エランガワ)を復活させたものである。地球環境ファシリティー(GEF)、環境省、国連開発計画(UNDP)が主導する「環境的に影響を受けやすい地域における生物多様性保全と生態系サービスの持続性強化プロジェクト」は、カンドゥルガムワGN部門でこのシステムを復活させ、村に目に見える変化をもたらした。
ハバラワッテは、森林局と野生生物保護局が管理する保護地域、カハラ・パレケレの森とサンクチュアリに隣接している。保護区に隣接する村は、生物多様性の保全と生態系のバランスにとって不可欠である。このため、ハバラワッテは環境的に敏感な地域(ESA)に指定された。ESAは重要な生物多様性を含み、重要な生態系サービスを提供している。パイロット・プロジェクトでは、コミュニティと協力して、長らく使われていなかったエランガワ・カスケードを復元することに重点を置いた。
チャンピオンの誕生
この取り組みを通じて、ESAプロジェクトは持続可能な土地利用計画と管理手法を復活させ、現在では、重要な環境的影響を受けやすい地域を保護しながら、コミュニティが安定した経済的利益を得ることを可能にしている。「ハバラワッテ農民協会のニール・ジャヤワルダナ会長は、「私たちは、古代王のエランガワについて聞いたことはあっても、見たことはありませんでした。「以前は、雨が降る年に一度しか農作業ができませんでしたが、このプロジェクトが始まってから、すべてが変わりました」。
改修される前のハバラワッテの廃タンクは、2千年以上前に古代シンハラ人によって開発された複雑な灌漑システムの一部だった。カスケード式タンク-村落システム(エランガワ)とは、乾燥地帯の微小集水域に組織された一連のタンクや小規模貯水池のことである。