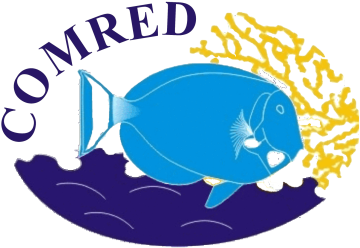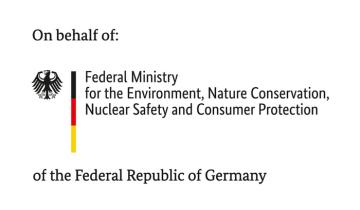クワレとタンガにおけるマングローブ保護と生計のためのジェンダー包括的養蜂事業

IKI-BMUKNが資金提供したプロジェクト「ケニア・クワレとタンザニア・タンガにおける沿岸および海洋生物多様性の越境保全と持続可能な管理 」は、コミュニティ・ベースかつジェンダーを包含したアプローチを通じて、海洋および沿岸の生物多様性の保全を支援している。マングローブ生態系への圧力を軽減するため、プロジェクトはクワレとタンガの地域コミュニティに代替生計として持続可能な養蜂を導入した。 指導者訓練は2部構成で行われる:第1部はミツバチの巣箱の建設、コロニーの管理、ハチミツの生産に焦点を当てる。第2部は蜂蜜が収穫できるようになったときに実施され、キャンドルや軟膏などの製品を作るための蜜蝋の利用など、加工や付加価値付けのスキルを身につける。指導と包括的なトレーニングの設計により、以前は文化的タブーによって排除されていた女性たちも、今では養蜂に積極的に参加するようになった。このプロジェクトは環境保護と地域の収入創出の両方を支援している。
コンテクスト
対処すべき課題
- マングローブ生息地の劣化
クワレ郡(ケニア)とムミンガ郡(タンザニア)のマングローブ生態系は、木材や非木材製品のための持続不可能な開発、農業への転換、水産養殖、汚染による大きな脅威に直面している。 - 低いハチミツ生産量と質の低さ
限られた養蜂技術、標準以下の巣箱と設備、不十分な収穫技術により生産量は低く、その結果ハチミツの品質も悪い。クワレとムキンガのハチミツのバリューチェーンには、体系的な市場とのつながりや付加価値活動が欠けており、コミュニティの収入の可能性を制限している。 - 限られた技術能力
地元の養蜂家、改良普及スタッフ、大工の技術が不十分で、トレーニングを受けていないため、巣箱の稼働率やハチミツ生産に大きな影響を与えている。 - ジェンダーに基づく養蜂からの女性の排除: ケニアの沿岸コミュニティでは、何世代にもわたって養蜂は男性優位の行為と見なされており、伝統的・宗教的規範に深く根ざしている。 そのため、女性は蜂蜜生産による経済的・社会的利益を得ることができない。
所在地
プロセス
プロセスの概要
つのビルディングブロックは、持続可能なコミュニティ主導の養蜂を支援する統合プロセスとして機能するように設計されている。最初のバリューチェーン分析(ビルディング・ブロック1)は、知識のギャップ、設備の欠陥、的を絞った介入の機会を特定することで、基礎を提供した。この結果、質の高い蜂の巣の不足に対処し、改良された設計を用いた現地生産を可能にする大工トレーニング(建物ブロック2)の開発につながった。高品質な巣箱が地元で入手できるようになったため、プロジェクトは能力構築の第一段階(構築ブロック3)を実施し、選ばれたコミュニティメンバーと政府職員に、巣箱を効果的に管理し、知識を共有するための実践的・理論的スキルをトレーナー研修モデルを通じて習得させた。ハチミツの生産が始まると、第2段階(ブロック4)の研修では付加価値と製品開発の実地指導が行われ、参加者は地元の材料を使って蜂の巣製品を加工・販売できるようになった。これらのブロックを組み合わせることで、診断から能力開発、製品開発まで段階的なアプローチが可能となり、生態系と経済的な成果を高めることができた。
ビルディング・ブロック
マングローブ蜂蜜のバリューチェーンの分析
このプロジェクトは、クワレ(ケニア)とムミンガ(タンザニア)でマングローブ蜂蜜の綿密なバリューチェーン分析を実施し、保全と地元の生計を支える戦略的介入策の指針とした。ValueLinksの手法を用い、養蜂家、投入資材供給業者、大工作業場、改良普及サービス、貿易業者、消費者など、バリューチェーン全体の関係者と流れをマッピングした。特定された主な課題には、標準以下の巣箱設備、生産量の少なさ、トレーニングの不足、市場とのつながりの弱さなどがある。ほとんどのハチミツは地元で販売され、付加価値は最小限に抑えられている。分析の結果、マングローブ蜂蜜をニッチなエコロジー製品としてブランド化できる可能性があることがわかった。推奨事項には、養蜂家や大工の訓練、巣箱の個人所有の促進、蜂蜜収集センターの設立、市場アクセスの強化などが含まれた。この分析により、プロジェクトの介入が現場の現実に直接対応することが確実になり、その後の能力開発とマーケティング活動の基礎が築かれた。
実現可能な要因
WWF、WCS、IUCN、CORDIO、Mwambaoといった積極的な技術パートナーの存在により、分析に有益な強力なサポートネットワークが構築された。クワレとタンガの両地域では、地元の大工や投入資材供給業者がすでに巣箱を生産しており、実用的な入口となった。養蜂家や政府職員は、現地訪問やインタビューで生産データや率直な洞察を提供し、ValueLinksの手法の使用はマッピングプロセスの構成に役立った。
- 養蜂家、政府職員、NGOなど主要なステークホルダーからの参加と意見。
- 過去の養蜂の取り組みから得た既存のデータと現地の知識。
- 明確な方法論(標準化されたアンケート、半構造化インタビュー、現地観察)により、一貫性のある検証可能なデータ収集ができたこと。
教訓
プロジェクトの初期段階でバリューチェーン分析を行ったことで、介入策を実際のニーズに合わせることができた。養蜂家の課題、例えば巣箱の質の低さ、生産量の少なさ、不十分なトレーニングなどは、的を絞った支援で対処可能であった。グループ養蜂場は非効率的であることが多かったため、個人の所有を促進することで成果が向上した。マングローブハチミツの需要はブランド化と収入創出の機会をもたらすが、品質管理と集約への投資が必要である。また、チェーンをマッピングすることで、付加価値におけるギャップが明らかになり、特にトレーナー研修のアプローチによる研修と指導の重要性が浮き彫りになった。
ミツバチの巣箱改良のための大工訓練
Kwale(ケニア)とMkinga(タンザニア)の両地域では、地元で生産される蜂の巣はしばしば標準以下であり、コロニーの稼働率が悪く、ハチミツの収穫量が少ない原因となっていた。そこでプロジェクトは大工工房を特定し、選ばれた大工に改良型ケニア・トップ・バー・ハイブ(KTBH)やその他の標準モデルの生産に関するトレーニングを実施した。クワレでは、2つの工房(Lunga LungaとTiwi)が対象となり、Lunga Lungaではすでに大規模な巣箱を生産していたが、技術的な改善が必要だった。Mkingaでは、Tanga市でトレーニングが行われた。研修では、巣箱の正しい寸法、適切な材料、基本的なハチの生態を強調し、大工が各設計の機能性を理解できるようにした。トレーニング終了後、ワークショップでは地元の需要に応じた巣箱の生産が継続され、コミュニティメンバーは寄付に頼らず巣箱を購入できるようになった。これによって地域のオーナーシップが確立され、巣箱供給の持続可能なモデルが確立された。この介入はまた、養蜂家への追加的な支援の土台を築き、養蜂家は地域内でより良い設備にアクセスできるようになった。
実現可能な要因
クワレとタンガにある既存の大工工房は蜂の巣作りの経験があり、技術向上に前向きだった。養蜂トレーニングが拡大するにつれ、地元では巣箱の需要が高まっていた。このプロジェクトは、トレーニングを指導できる技術専門家へのアクセスがあり、養蜂担当官や経験豊富な養蜂家からのインプットにより、実践的な妥当性が確保された。この研修は、市場の明確なギャップからも恩恵を受けた。この介入以前は、標準的な巣箱が入手できなかったり、手が出なかったりした。
- コミュニティ内に熟練した地元の大工がいる。
- 巣箱建設に適した地元の資材が入手できたこと。
- ミツバチの生態に直結した、トレーナーによる明確なガイドラインと標準仕様。
教訓
地元の大工は積極的に参加し、大量注文にも対応できたが、専用のトレーニングを受けなければ、重要な設計上の特徴を理解することができなかった。トレーニングの内容は木工にとどまらず、巣箱の機能性と点検のしやすさを確保するためのミツバチの生態も含まなければならない。標準以下の巣箱生産は稼働率の低さにつながり、生計手段としての養蜂への信頼を低下させる。継続的な品質管理は依然として課題であり、フォローアップ支援を通じて対処すべきである。このモデルは、大工が地元市場に溶け込み、養蜂家と直接交流することで最も効果的に機能する。また、大工を育成することで、地域経済を寄付主導型からコミュニティベースの起業家精神へとシフトさせることができる。養蜂家、改良普及指導員、大工が共通の理解を持つことで、巣箱の設計と管理方法のずれを回避することができる。このアプローチの成功は、バリューチェーンの上流アクターを支援することで、エンドユーザーの成果を改善できることを示している。
持続可能な養蜂実践のためのトレーナー・トレーニング
クワレとミキンガの養蜂家は、改善された巣箱管理に関する知識が乏しく、低収量、器具の扱いの悪さ、基本的な養蜂実践に対する自信のなさに苦しんでいた。このギャップに対処するため、プロジェクトは持続可能な養蜂実践に関する包括的なトレーナー研修(ToT)プログラムを実施した。参加者には、選ばれた養蜂家、女性、若者、家畜生産担当官が含まれました。研修では、ミツバチの生物学と生態学、養蜂場の場所選び、コロニーの管理と増殖、害虫と病気の防除、受粉サービス、養蜂器具、記録の管理、農薬がミツバチに与える影響など、主要なトピックに焦点を当てた。また、巣箱製品やこの分野における最新の研究も取り上げられた。参加者が知識を即座に自信を持って活用できるよう、実践的な実地学習が重視された。改良普及員が参加したことで、プロジェクト終了後も養蜂家を支援する組織的能力が向上した。研修を受けた人々は、その知識を伝え、コミュニティで他の人々を指導することが期待され、改善された実践方法をより広く普及させ、マングローブ地域の自然に根ざした生計手段としての養蜂の長期的な持続可能性に貢献した。
実現可能な要因
- 地元政府やコミュニティ・グループの積極的な関与と支援。畜産担当官が関与することで、組織的なオーナーシップが高まり、豊富な飼料と水が存在することで、技術的な改善が直接的な効果をもたらした。
- 実践的なデモンストレーションに適した養蜂場の確保。 実践的な研修アプローチが鍵となった。
- 理解度を高めるために、利用しやすい研修資料と現地語の説明を使用したこと。
教訓
実地研修がないため、多くのグループは基本的な巣箱の管理、収穫技術、熟した蜂蜜の見分け方などで苦労していた。そのため、収穫量が少なかったり、コロニーが逃げ出したり、収穫した蜂蜜が腐ってしまったりすることもあった。ToTモデルは地元での知識の共有を可能にしたが、学習を強化しスキルギャップを避けるためには、フォローアップの指導が不可欠である。研修に行政官を参加させることは、生産者と支援サービスの橋渡しになり、有益であることがわかった。場合によっては、畜産担当官には実演用具がなく、巣箱管理の事前研修も受けていなかったため、コミュニティを支援する能力に限界があった。研修では、実演だけでなく、実際の巣箱を使った実習も行う必要がある。将来的には、ToTは常に再教育コースとファシリテーションを受け、コミュニティで継続的なピアサポートを提供する必要がある。
地元で入手可能な素材を使ったミツバチ由来の製品づくりによる付加価値向上
クワレで実施された養蜂研修の第2フェーズは、ポストハーベスト処理と蜂の巣製品の付加価値に焦点を当てたものであった。この研修は、第1フェーズで習得した技術スキルを補完するためのフォローアップ研修として実施された。参加者は養蜂ToTと、巣箱から蜂蜜を収穫したことのある選ばれたグループメンバーであった。研修では、適切な収穫技術、衛生管理、生はちみつと蜜蝋やプロポリスなどの巣の副産物の加工方法について学んだ。実習では、参加者が蜜蝋キャンドル、ボディクリーム、リップクリーム、ローションバー、火傷の軟膏、咳止めシロップなど、さまざまな市販品を作ることができた。パッケージや製品のデザインには、ココナッツの殻、竹、リサイクルガラスなど、地元で手に入る材料が使われた。研修では、製品の品質、賞味期限、市場性を向上させるためのブランディングに重点が置かれた。この段階では、参加者が伝統医療やパーソナルケアにミツバチ製品を使用するアイデアを共有することで、技術革新や仲間同士の交流も促進された。付加価値の向上は養蜂家の収入の可能性を強化し、マングローブに適合した持続可能な生計を立てるという、より広範な目標を支援するものである。
実現可能な要因
参加者はすでに第1回目の研修で実践的な経験を積んでおり、知識を深めようという意欲に燃えていた。先に設置された巣箱から収穫された蜂蜜が入手できたため、すぐに実践的な練習ができた。トレーナーたちは、地元の材料を使った製品の処方やパッケージングの経験をもたらした。地元の組織や集合場所からの支援は、将来の販売への道筋を作った。天然製品に対する地域社会の関心は、付加価値を実行可能な収入源として位置づけるのに役立った。
教訓
参加者の多くは、蜂の巣製品の加工に関する予備知識がなく、実践的で実践的なアプローチを高く評価した。付加価値のある製品の選択肢を示すことで、特に女性参加者の自信と意欲が高まった。パッケージングに身近な地元産の材料を使うことで、コストを削減し、農村部の生産者との関連性を高めることができた。トレーナー研修のアプローチで強調されたピアラーニングは効果的で、参加者の中には、正式なアグリゲーションモデルが導入される前から、付加価値について他の参加者の指導を始める者もいた。参加者のトレーニングは1回だけでは不十分で、製品の品質と市場対応力を向上させるためには、再教育セッションと継続的な支援が不可欠である。全体として、生産と付加価値を結びつけることは、巣箱のオーナーシップの強化と養蜂への長期的なコミットメントを促した。
影響
社会経済的:
- 既存の巣箱のコロニー化が進み、新しい巣箱の数も増加した。
- いくつかの養蜂グループではハチミツの収穫量が向上した。例えば、Tunusuru グループは、わずか 2 つの巣箱から 14kg の未熟で発酵した蜂蜜から 25kg の完熟した蜂蜜を採取し、巣箱 1 つあたり 12.5kg と平均の 10kg を上回る収量を達成した。
- 21人の女性が巣箱の管理と付加価値付けの研修を受け、家計収入に貢献し、地域社会の認識を変えた。
- ミツロウキャンドル、リップクリーム、ボディクリームなど、7種類のミツバチ製品を地元で生産している。
受益者
- ケニア・クワレ郡とタンザニア・ムキンガ郡の養蜂グループと地域住民
- 収入を得る機会が限られていた女性や若者たち
- 巣箱建設トレーニングを受ける地元の大工たち
グローバル生物多様性フレームワーク(GBF)
持続可能な開発目標
ストーリー

変化の鼓動:養蜂とユンギの女性たち
潮が引き、光り輝く砂地に細い道が現れる。海が再び通り道を取り戻す前に、ユンギに徒歩でたどり着く唯一の道だ。ケニアの南海岸に浮かぶこの静かな島では、時間がゆっくりと流れているようだ。夜が明けると、ユンギは交通音や機械音ではなく、自然のメロディーに包まれる。古代のカヤの森から鳥の鳴き声が聞こえ、うっそうと茂る雑木林を縫って野生の花の蜜を集めるミツバチの定常的な鳴き声と混ざり合う。ここは大地が語りかける場所であり、ここに長く住む者は耳を傾けることを学んだ。
ユンギで唯一の水場で、私たちはカディジャと彼女の女友達がこれから養蜂場で使う水を汲んでいるのを見つけた。彼女はこの土地が変わり、人々が潮の満ち引きのように移り変わるのを見てきた。彼女の子供たちはここで育ち、小さな足でマジョレニのマングローブ林を通り過ぎ、学校へ通う同じ細い道を歩いた。
子供の頃、父親から養蜂を教わった。4つの丸太の巣箱を点検するためにマングローブ林や近くの森に姿を消し、何週間も何カ月もかかるかもしれない買い手を待って、大切に保管した黄金色の蜂蜜を持って帰ってきたことを彼女は覚えている。この島は孤立しているため、金銭、貿易、進歩のすべてが遅々として進まなかった。彼の古い巣箱に自分の巣箱を2つ加えて6つに増やし、コムレッドからラングストロスの巣箱を5つ譲り受けた。
収穫のたびに、彼女は20リットルのジェリカンに蜂蜜を詰め、買い手を辛抱強く待った。何年もの間、彼女はハチミツを1kgあたり250KShというわずかな値段で売り、その本当の価値を知ることはなかった。長女である彼女には他に選択肢がないことを知りながら、家族を養うために養蜂と並行して農業を営んでいた。養蜂は遺産だが、生き残ることは義務だった。養蜂研修に参加して初めて、彼女は真実を知った。自分の蜂蜜を正しく加工すれば、1kgあたり1,000KShで売れるというのだ。ハチミツを正しく加工すれば、1キログラムあたり1,000KShも売れるのだ。ハチミツは単なる伝統ではなく、生命線であり、より大きなものへの架け橋だったのだ。
そして今、彼女はその橋を架けようとしている。 それは彼女のトレーニングから借りてきた言葉だが、彼女の世界ではそれ以上の意味がある。それは、困難を乗り越え、仲間を導き、誰も取り残されないようにすることだ。家長として、彼女が先に歩き、他の者が後に続く。
ユンギの女性たちは、自分たちの巣がいっぱいになり、コミュニティが繁栄するまで、どんなことにも立ち止まらない!
(出典:COMRED)