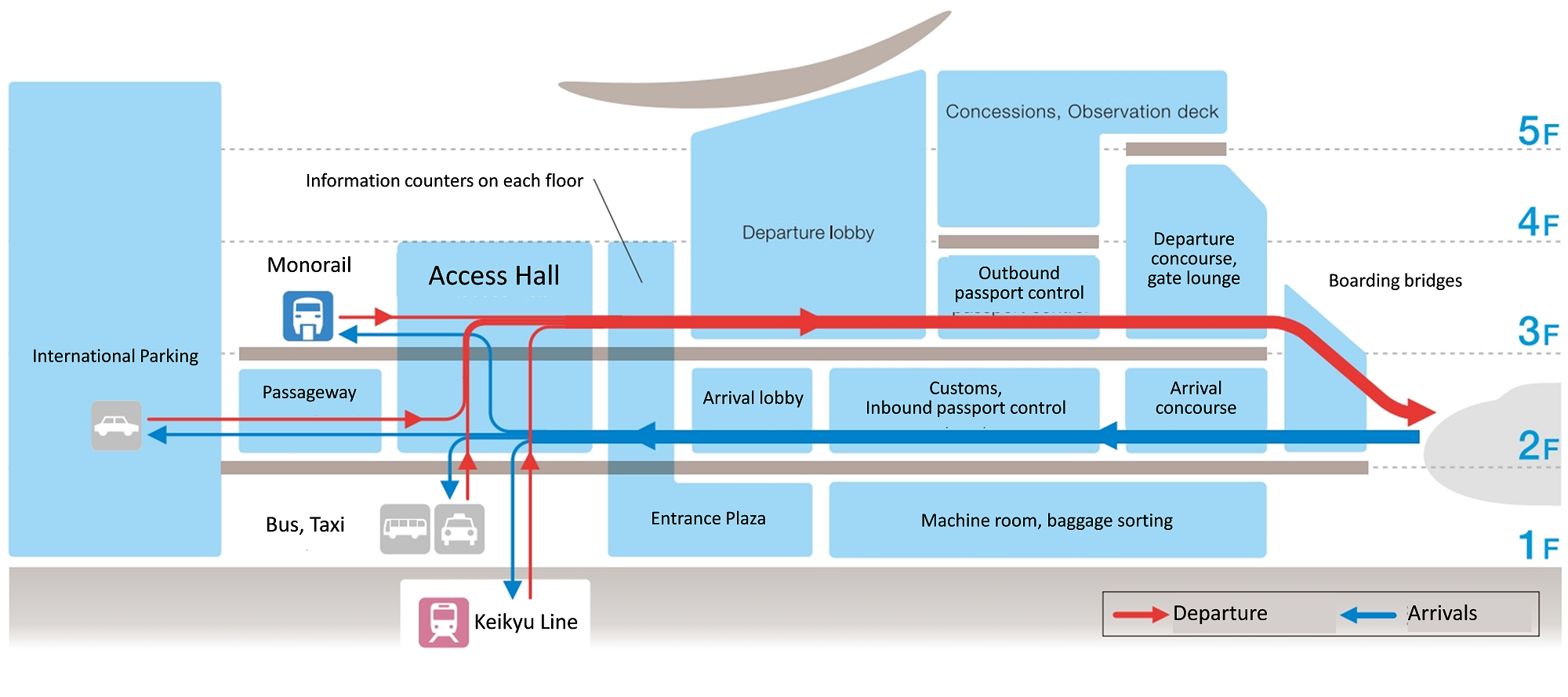資源投資プロセスへのステークホルダーの参加を保証するためのガバナンス体制の構築。
ラ・ミンガの対象となる保護地域はすべて、コミュニティ協議会と地域の環境当局によって管理されている。ラ・ミンガの純益は、保護地域の管理計画の実施を支援するため、コミュニティ協議会(Community Councils)やその他の非営利団体に譲渡される。
ラ・ミンガの純益は、保護区の管理計画の実施を支援するために、コミュニティ協議会やその他の非営利団体に譲渡される。
ラ・ミンガのための技術委員会が、ラ・ミンガ基金収入の使途を指示・監督し、毎年、Fondo Acciónが開設・保有する口座に振り込まれる。
フォンド・アクシオンが開設し、保有している。技術委員会は、コンサベーション・インターナショナル・コロンビア、フォンド・アクシオン、地元の環境当局、保護区管理に参加するコミュニティ協議会の代表者、および学術顧問で構成される。技術委員会は、地域環境当局とフォンド・アクシオンの双方から提示された年次投資計画を検討し、承認する。
技術委員会は、地域環境当局と地域評議会の両方から提示された年次投資計画を審査し、承認する。
執行委員会は、技術委員会から提出された勧告に従って資金提供を決定する。
ガバナンス・メカニズムに求められる透明性と、コミュニティ協議会の代表と環境当局の効果的な参加を保証する必要性が、ガバナンス・メカニズムを可能にする大きな要因である。また、提案とプロジェクトの徹底的なフォローアップも、このメカニズムが機能するための重要な要素である。そして最後に、提案が管理計画と優先順位付けされたニーズに沿ったものであることを保証するために、地元の利害関係者との能力構築プロセスを継続することが非常に重要である。
私たちは、自分たちのニーズを満たすために利用する地域の管理について、ルールを受け入れ、地元の利害関係者に権限を与えるためには、最初からコミュニティの関係者の参加が必要であることを学んだ。また、このような仕組みの構築には多くの時間が必要であり、早い段階から財政的支援を期待しないよう、すべての協力者にそのことを明確に伝えることが非常に重要であることも学んだ。
共同管理メカニズムの構築には、公的機関がコミュニティからのインプットの価値を理解し、地元の利害関係者のニーズに従って投資の必要性に優先順位をつけてくれることが必要である。
最後に、寄附金はさまざまな関係者に多くの誤った期待を抱かせる可能性があること、そして国、地域、地方レベルに届くようなコミュニケーション戦略を確立する必要があることを述べておく。