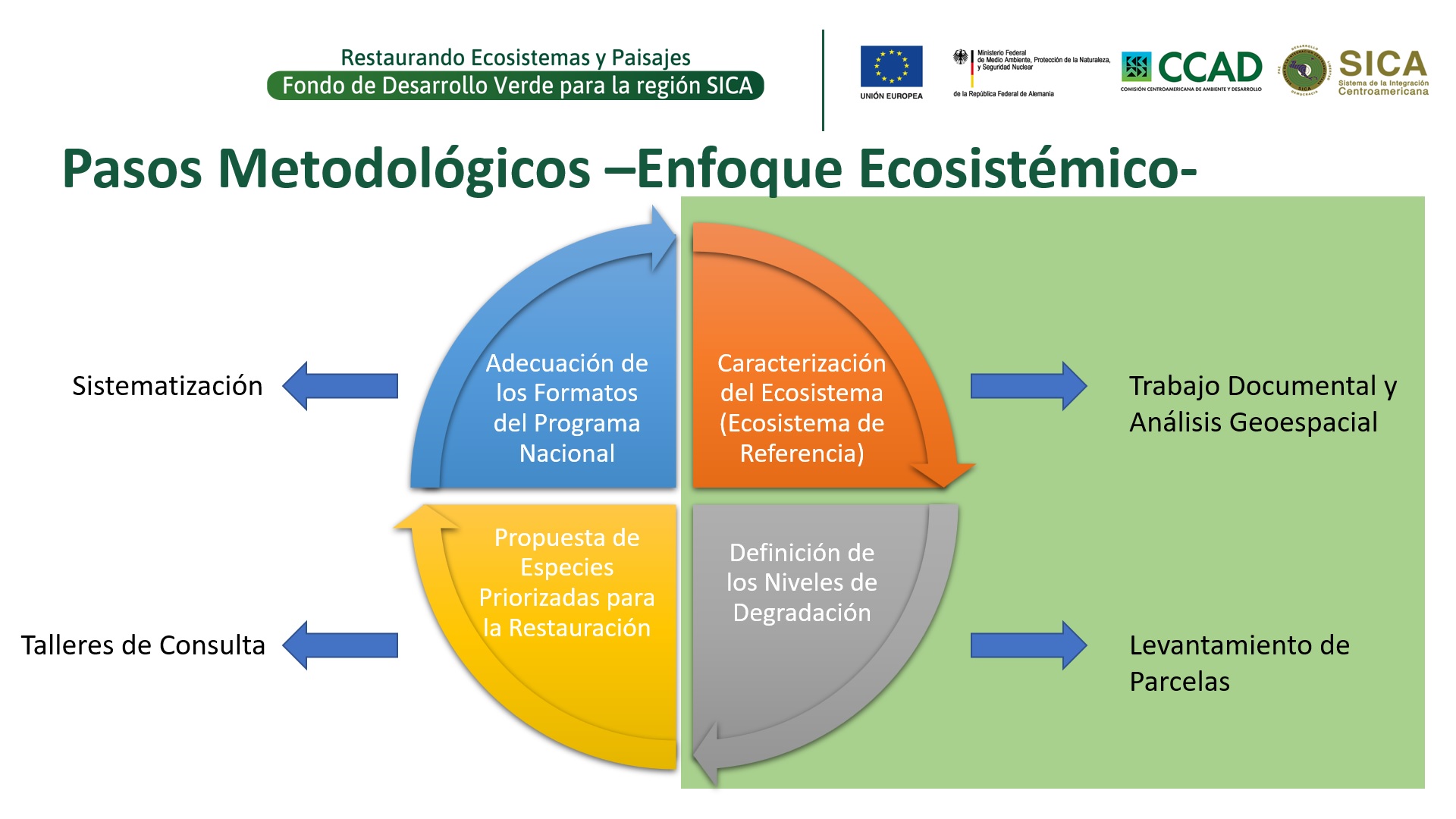インターナショナル・アライアンスには現在3つのワーキンググループがあり、メンバー自身がリーダーとなり、アライアンス 事務局のサポートを受けています。各ワーキンググループは1~2名の議長によって率いられ、継続的な作業プロセスを確保するため、6~8週間ごとに会合を開いています。
現在、以下のワーキンググループがあります:
- 科学政策インターフェース(議長:スー・リーバーマン、WCS)
野生生物に対する私たちの基本的な理解を踏まえ、科学的根拠に基づいたこの理解を国際的な政治プロセスに反映させたいと考えています。
- 変革的システム変更:全体像(司会:アレックス・D・グリーンウッド、IZWベルリン、バラバラ・マース、NABU)
アライアンスの目的と目標を達成するためには、根本的な障害が存在する。これらを特定し、対処することがこのワーキンググループの焦点である。
- 評価/効果的な介入(議長:クレイグ・スティーブン、ワンヘルスコンサルタント)
効果的な介入に関するグッドプラクティスをアライアンスメンバーから集め、セクターや地域を超えた学習と知識交換を可能にすることを目的とする。