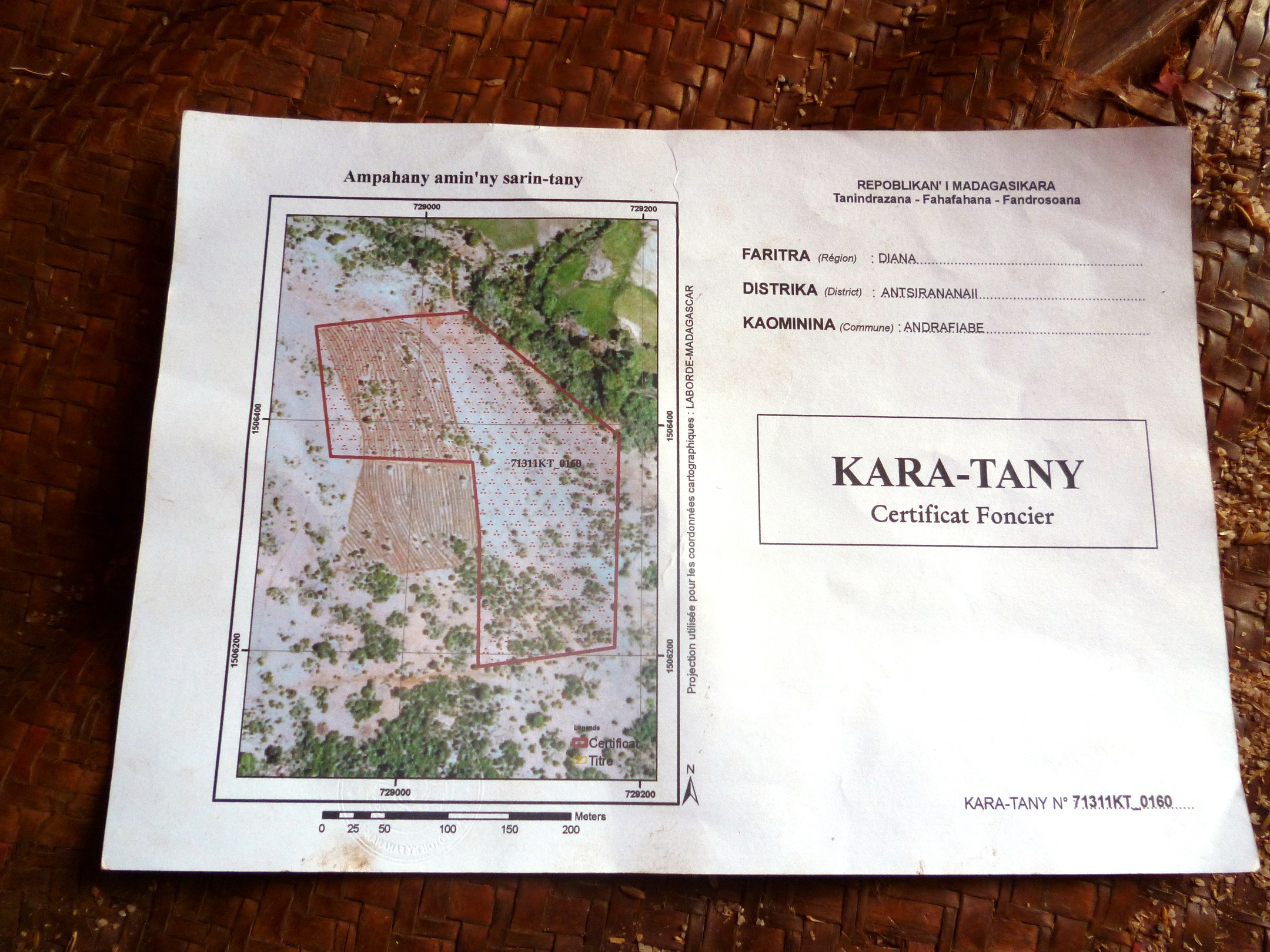創造的なプロセスが始まり、アイデアが計画に変わり、何が達成できるかについて大きな期待が寄せられると、協会は、入手可能な製品をすべて漁獲して(単価の安い高値で)迅速に利益を得るか、高品質の製品を確保するために漁獲制限を設けて(より高く評価され、ブラックシェルの個体群がライフサイクルを全うできるようにする)長期的に利益を得るかというジレンマに直面した。
組合員にとっては、第二の選択肢の方が合理的と思われたため、漁獲制限を管理するツールを設計する必要があった。その解決策は、漁獲サイズを法定漁獲量の2ミリ上とし、いくつかの規制を漁業規則に採用することだった。つまり、狂気じみたアイデアから、組合員の総意による強力な制裁(金銭的制裁と組合員の漁業権の停止)を伴う規律ある実施に移行することだった。
より良い未来を実現するためには、自分たちの生き方を変えなければならないという確信。
自分たちの提案に自信を持ち、決断の不確実性を恐れないこと。
規律ある実行が重要な要素である。
管理職の責任を交代させることで、ほとんどの者が管理職の役割の重要性を理解し、互いを尊重するようになる。