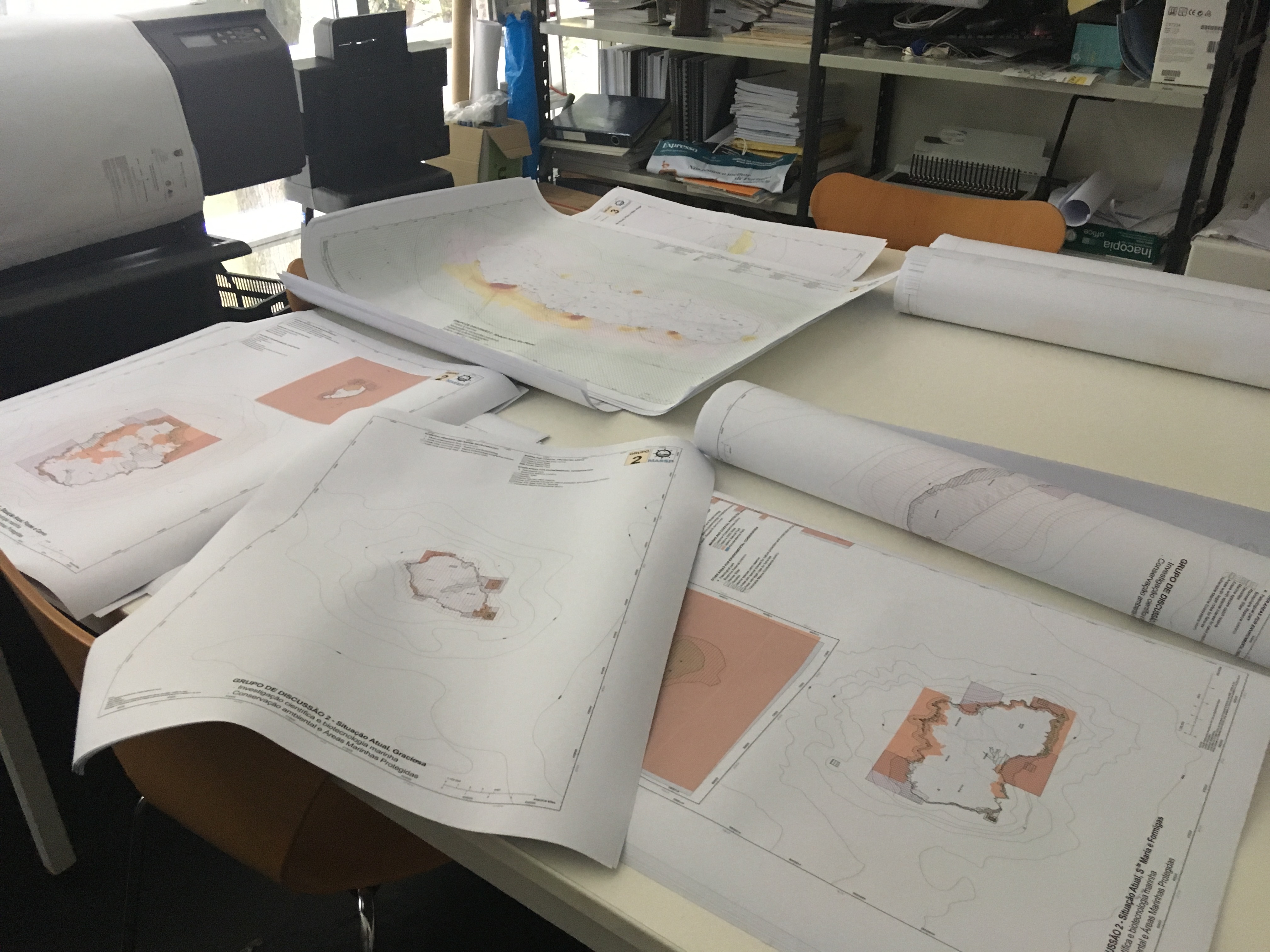(1) この島では、公園管理、観光サービス、その他の監視活動に関する仕事の機会を提供する。このような機会は、自分たちの文化や遺産を認識し、学び、その価値を再認識し、保護する青少年に力を与える。その価値が世界に認められることで、世代間の継承が促進される。
(2) 青少年に知識を伝えるために、年長者が参加することの重要性。管理には市民の参加が不可欠であり、地元の知識を活用できる可能性がある。
(3) 地元の人々がパークレンジャーとして従事することを許可することで、島に雇用を生み出し、ラパ・ヌイ・コミュニティの知識を利用して島の価値を伝え、その保護をよりよく監視することができる。
(4) マウ・ヘヌアと国家機関との間で、文化的に安全なプロトコルと、遺産保護の統一基準を尊重する同盟関係を確立する。
(5)手続きと手順を確立するための管理体制の構築と実施。