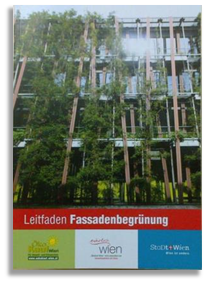国境を越えた共同管理目標の特定
最初のステップは、国境を越えた管理の問題に取り組む際に考慮すべきステークホルダー・グループを特定することである。自然保護、農業、林業、観光、調査、地域社会と自治体の6つのステークホルダー・グループが特定された。次にコア・チームは、意思決定分析プロセスに参加させるステークホルダーの代表を最大8人まで特定する。次に、参加する各公園当局が、それぞれのステークホルダー・グループの視点から、2~5つの懸念事項や要望を独自に特定する。次に、各コアチームは、希望や懸念を目標の記述に変換し、究極の目標と、究極の目標を達成するための手段でしかない中間目標とを区別する。そして、利害関係者グループ間の主なトレードオフと懸念を表すと同時に、焦点となる国境を越えた保全活動の成功の尺度として機能する、3つの究極の定量化可能な目標が特定される。より少ない数の究極の目標に焦点を当てることで、参加型意思決定分析を実施するための実現可能性と理解しやすさが確保される。
目的とステークホルダーが、参加する2つの公園のどちらか一方に振り回されるのを避けるため、ステークホルダーグループと目的の初期リストは、各パイロット地域の2つの公園の公園当局からの独立したインプットに基づくべきである。 8人以上のステークホルダー代表(公園当局を含む)からなるグループには、専門的なファシリテーターが必要になる可能性が高く、参加型意思決定に関する問題に対処するために、ここで説明したプロセスを大幅に変更する必要がある。
公園当局は、当初の18の目的セットを階層構造に整理して目的間の相互関係を認識し、「クマと人間の共存の維持」を究極の目的とすることが有用であると考えた。 決定分析のために、チームは以下の最終目標を選択した:1) 越境地域とそれ以遠における熊の生息能力の維持、2) 越境地域における持続可能な農業の維持、3) 熊の管理に関する利害関係者の対立の最小化。
ステークホルダー・ワークショップのアンケートでは、回答者の半数が、最終目的は明確に理解されており、彼らの懸念を代表していると回答した。利害関係者の中には、次のような問題が十分に取り上げられていないと指摘する者もいた。クマの実数、エコツーリズム、クマによるプラスの影響、クマ管理と地域社会との関係、クマの生態学的要件、関連する規制(国および地域)、現実的な日々の問題。