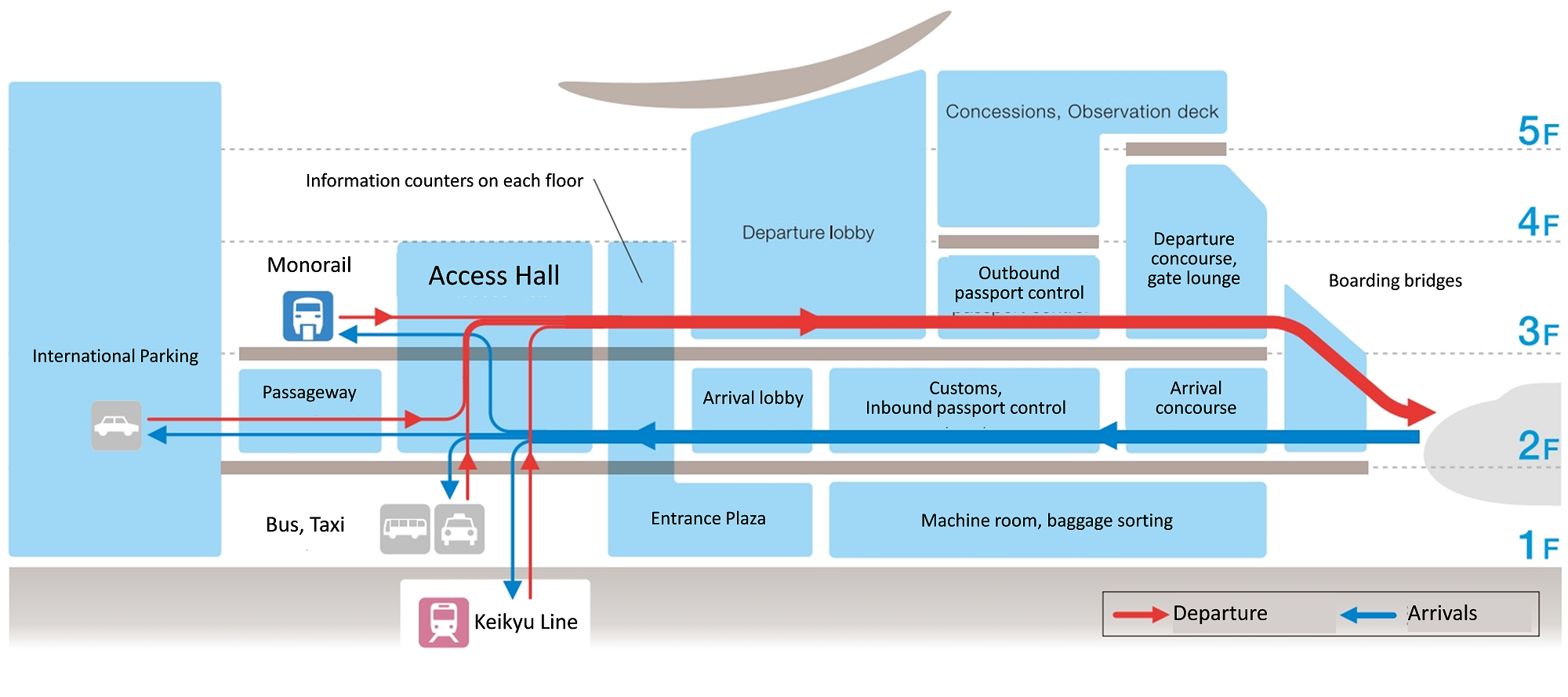分散化されたゾーン・ネットワーキングは、ある地理的地域のメンバー組織が1つのゾーンに集まる形で運営されている。これによって、地理的な位置関係に基づいて同じような課題を経験しているメンバーが一堂に会する。
メンバーは意思決定プロセスに参加することができ、全国ネットワークのさまざまなイニシアティブにおける代表は、ゾーンの代表と決定に基づいている。
そのため、同じゾーンのメンバーは、同じゾーンのメンバー組織と関わるために必要な時間や資源が限られているため、費用対効果の高い方法でより多くの会合を開くことができる。
また、同じゾーンのメンバーは、各地域で共同してアドボカシー活動に取り組むことができる。
メンバーを一定の地理的地域に集めることで、メンバーは互いを知り、交流を深め、メンバー同士の学習と共有を高める活動に取り組むことができる。
ゾーン・メンバーを巻き込んだ参加型プロセス:さまざまなゾーンに、そのゾーンに関わる決定を下す権限が与えられている。